教育の目的 (2)
自立とは、もうひとりの自分を育てること
自分の生き方を自分で決められるということは、誰からも支配されずに、物事を自分の力で決めるということである。
すなわち、自立の力を育てるということである。
幼い頃は誰でも自己中心的に生きている。
家族で出かけて、電車に乗る時間になっているのに、「アイスクリームを食べたい」と言ってダダをこねる。
親が「これから電車に乗るんだ。いまはガマンしなさい」と言いきかせる。
まわりを見て判断する力が育っていないので、親が決めてあげる。
中学生になっても、稀にこんな子がいる。
三者面談で受験する高校を決める時、先生が「○○さんは、どこを希望しているの?」と訊くと、「お母さん、どうしよう?」と。
また、こんな子もいる。
クラスメートとちょっとしたことでもめて、殴ってしまう。
ある子ががんばって学芸会で見事に演じて先生に褒められると、「あいつばかり、できやがって。ウゼーんだよ」と。
「いまはガマンしなきゃ」と自分にきかせる〝もうひとりの自分〟が育っていないからダダをこねるのだ。
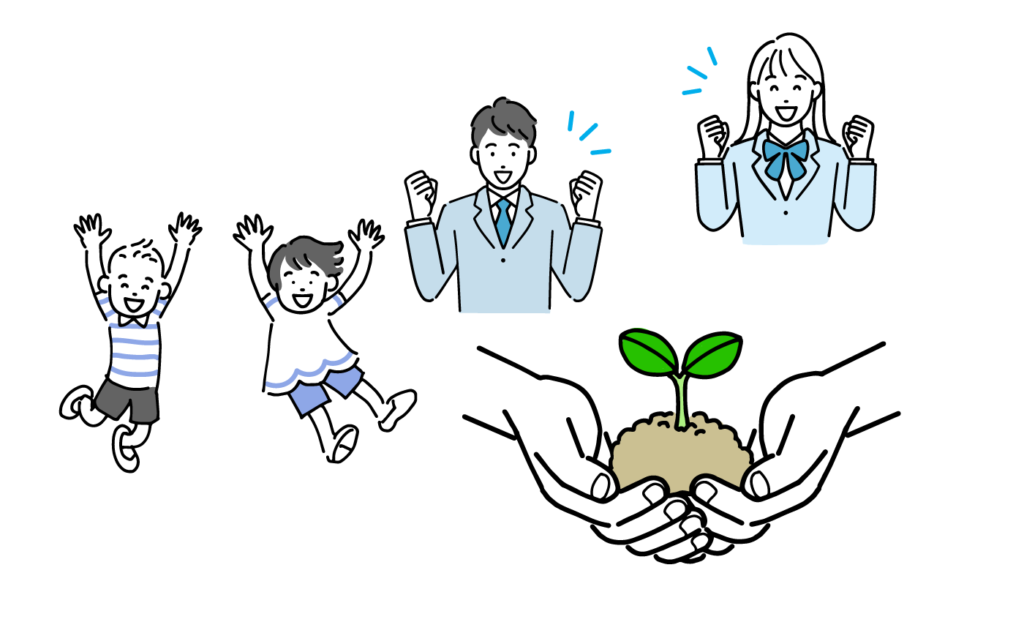
A校にするかB校にするか、悩むところだろう。
おおいに悩んで、先生や保護者に助言を得るすべ術も知って、「自分の進路だから自分で決めなくちゃ」と悟らせる〝もうひとりの自分〟を育てなければならない。
「そんなことで腹を立ててはいけない。どんなことであっても暴力はいけない。手を出してダメだ」と自分を叱る〝もうひとりの自分〟を大きくしないといけない。
クラスメートが成し遂げたことに共感して、その喜びや感動を分かち合う〝もうひとりの自分〟を伸ばさなければならない。
〝もうひとりの自分〟は、先生や保護者に褒められたり怒られたりしながら、また、学級集団で起こるもめごとを自主的に解決していく中で、助け合い励まし合う集団を築いていくなかで、だんだん育っていく。
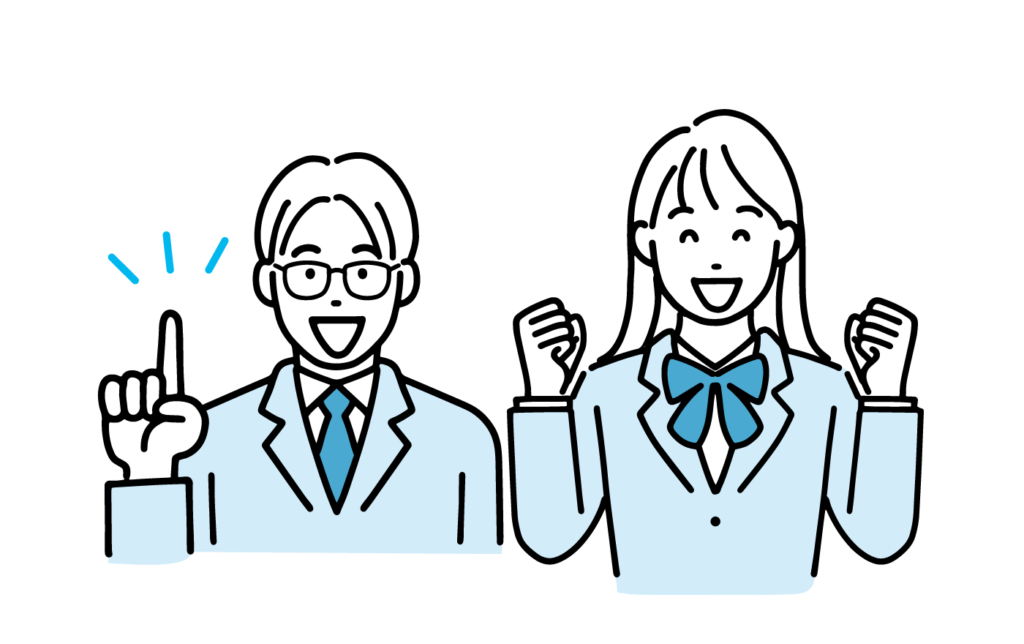
私は、過ちを犯した子どもには真剣に怒ったが、それはその子の全人格を否定するものあってはならない。
その子の心の中の育ちかかっている〝もうひとりの自分〟を刺激し励まし育てる意図で怒ったのである。
矛盾するようにみえるかもしれないが、〝共感的に怒る〟のである。
また、いじめなど学級集団の問題として起こることも多い。
集団の質が問われる。
子どもたちが主人公とした民主的自治的集団が築かれる中でこそ個人が成長していくことは。
度々述べてきたことである。
逆説的にいえば、失敗すること・過ちを犯すことは、〝もうひとりの自分〟を育てるチャンスだといえる。
学級集団づくりのジグザグらせん階段の過程で、一人ひとりの〝もうひとりの自分〟が育っていくのだろう。
(つづく)



コメント