自立の力を阻むもの③
先入観、固定観念
私は、神奈川県の公立中学校で36年間教員を務め、退職後長野県に移住してきました。
長野県は、自然が豊か、空気はきれい、水は美味しい、地産地消が進み食べるものは美味しい、人はせかせかしていない……、実に暮らしやすいところです。
長野県の自然の豊かさなどは耳学問としては知っていたつもりですが、暮らしてみてわかった良さが多く、終の住処にしようと決めています。
神奈川県の中学校で学んだことは多く後悔など全くありませんが、長野県がこんなによいところなので、はじめから長野県に就職すればよかったとさえ思います。
私は、長野県には旅行で来て良いところだと知ってはいましたが、本当の良さを知らなかったのです。
私は長野県に移住し余生をのんびり暮らそうと思っていたのですが、昨年から、社会科の教員が足りないと請われ、地元の中学校で社会科の非常勤講師を務めています。
私は神奈川県でしか教員の経験はありませんが、地方によって多少の違いはあるにせよ、学校のようすは大差ないだろうと思っていました。
ところが、地元の中学校へ行って、驚きの連続です。
県によってこんなに違うとは?
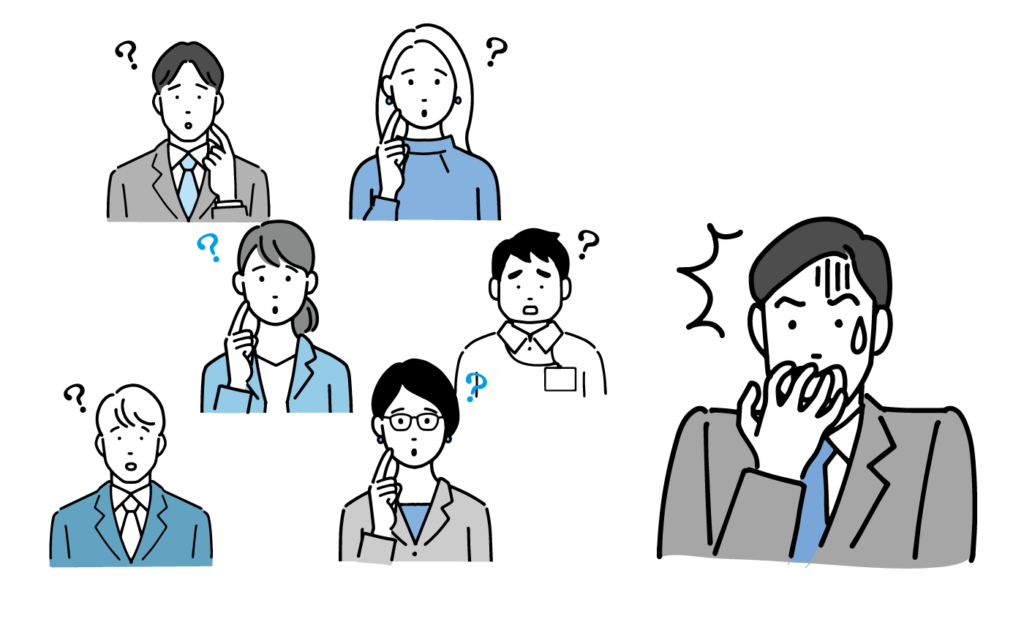
私は知らなかったのです。
どこも同じだろうという先入観・固定観念にとらわれていたのです。
「神奈川県ではこうでした」と話すと、地元の先生たちは驚きます。
私の価値基準で「これ、変でしょ!」ということが、地元の先生たちには「当たり前!」ということがたくさんあるのです。
〝知〟の重要性を改めて思い知ることになりました。
どちらが良いかわるいかは一度置いて、とにかく違うのです。
私の価値観は揺らぎました。自分の価値観は正しかったのか?と。
疑うことから始めよう!
知らないということに気づくことは難しい。
今回の経験は、何が正しいか自分で考え判断する〝自立の力〟を育てるには、自分がもっている価値観にたいして疑うことの重要性に気づかせてくれました。
自戒の念を込めて言いますが、自分の価値観、自分の考え、自分のやり方を疑ってみましょう。
本当にこれが子どもの自立につながるか? 自立の力を育てるために本当に必要なことは何か?
〝なぜ?〟〝本当は?〟という疑問が、学問を究めていく出発点ではないでしょうか。

教育学もまた然り。
いま「正しい」と思ってやっていることは、本当に正しいか?
いまやっていることで、本当に子どもが育っているのか?
いまやっていることを〝A〟としたら、〝B〟という考え方・選択肢はないのか?
疑うことから始めましょう!



コメント