自立の力を阻むもの③
〝当たり前〟を疑う
私は、神奈川県の中学校で30年以上教員をやっていました。
ほとんど毎年学級担任になり、毎年子どもを主人公にする自治のクラスをめざして学級づくりに取り組んできました。
繰り返し述べていますが、自治的なクラスをつくるために必要な3つの要素は、班とリーダー(班長)と討議です。
3学期には、教師の手を離れ、リーダーたちが指導力を発揮してクラスを自分たちで運営し、改善していくクラスにする、ということを目標にしていました。
若い頃は失敗も多く、なかなかそこまでいかないこともありました。
なんとか、そこまでいったかなと思えるようになったのは、10年以上たってからでしょうか(それでも失敗した年もありました)。
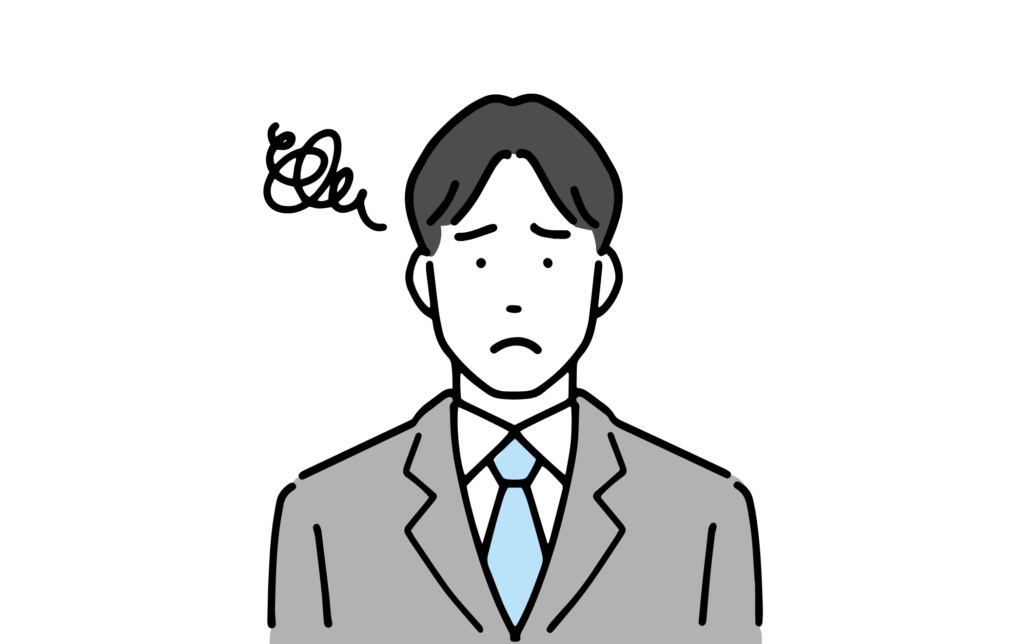
3学期になれば、帰りの会まで自分たちで運営し、自分たちで話し合い、要求を出しあって、一歩ずつクラスをよくしていくということできるようになりました。
私が忙しいときなどは子どもたちに任せました。
学級委員が、「帰りの会が終わりました。あと、〝先生から〟です」と職員室に呼びに来てくれました。
しかし、そこで終わりではないはずです。
教育の仕事に終わりはありません。
学級集団がさらに育ち子どもたち一人ひとりの自立の力が伸びれば、リーダーが必要なくなるはずです。
また、クラスが学習集団としてさらに成長するならば、学問にたいする飽くなき探求が自治的に深められていくはずです。
ですから、私はせめて2年生から3年生は、クラス替えせずにもち上がりたいと思っていましたが、私がいた学校では毎年クラス替えするのが当たり前、そこを崩すことはついにできませんでした。
私自身、この当たり前に抗することを諦め、他の職員に「もち上がりでやってみませんか」と提案することさえやめてしまいました。
3学期の到達度を超えたことはありませんでした。
それは私にとって未知の世界のままで終わってしまいました。
ところが、長野県では…
縁あって、昨年から勤めている長野県の公立中学校では、私にとっては信じられないようなことが次々と…
その一つが、なんと3年間クラス替えがないのです。
私の〝当たり前〟が壊されました。
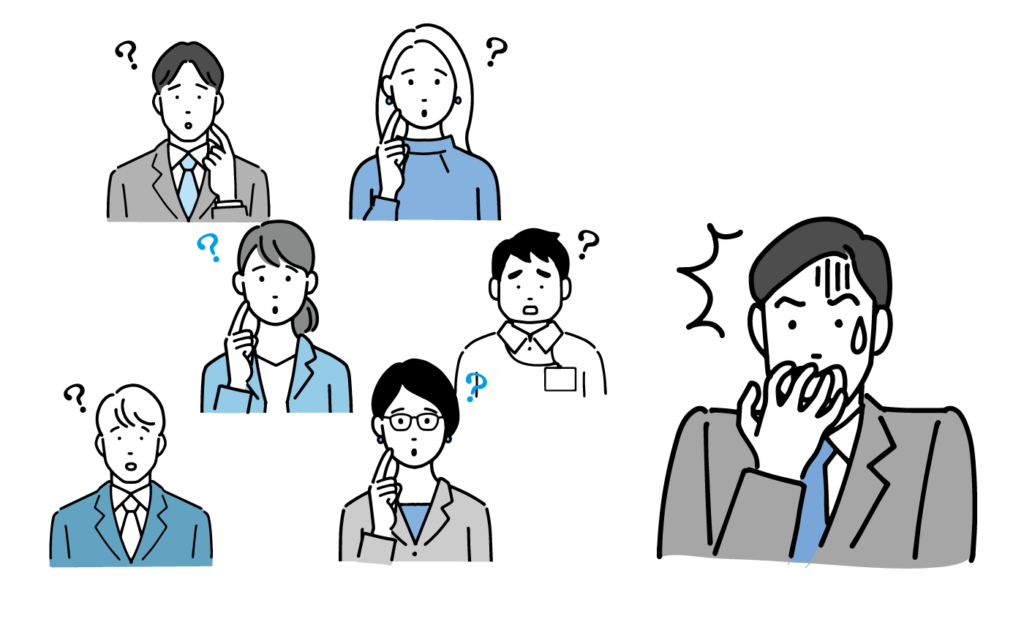
私は、非常勤で教科(社会科)の授業だけ受け持つという契約なので、学級担任はできないのですが、「学級担任ができたらなあ…」と叶わぬ夢を見ています。
知りませんでした。
3年間同じ学級集団で自治を高められれば……
知らないということは、本当に恐いことです。



コメント