道徳教育について考える(3)
道徳の教科化について〔2〕
「道徳」教科化への政策動向とその批判㊥
立憲主義の危機のもとですすむ教育改革
櫻井 歓(日本大学)
安倍政権による立憲主義の否定
「道徳」の教科化を推進する立場、あるいは教科化への期待といったものは、実際には多様であると考えられます。あえて類型化するならば
- 愛国心の育成を重視して日本の伝統の中心に天皇制を置くような復古的立場
- 思いやりや社会規範を育ててほしいといった世論調査に現れるような国民の素朴な期待
- いじめや情報モラルなど今日的な課題への対処を「道徳」に期待する立場
などに整理できるでしょう。
しかし、現在すすめられつつある「道徳」教科化の政策が、安倍政権のもくろむ「立憲主義の否定」という政治的文脈のもとにあることは見逃せません。
前回の第1次内閣期(2006~07年)と今回(2012年12月~)とに共通する安倍政権の特徴として、戦後教育改革以来の理念と制度を否定する方向での教育改革を強力に推進する点と、「憲法改正」のプロセスを具体化していく点とを挙げることができます。
第1次内閣の時期には、小泉内閣から引き継がれた教育基本法の全面改定を実現し、教育再生会議ではいじめ問題や「徳育」の教科化などについて提言がおこなわれたのと並行して、いわゆる憲法改正国民投票法が成立しています。
第2次内閣となってからは、教育再生実行会議を中心に教育改革が次々に提言されるとともに、憲法96条(憲法改正の手続き)の改定や、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更(憲法9条の解釈改憲)が現実的な政治課題にのぼっています。
安倍政権において教育改革と「憲法改正」とは別個のものではなく、国家を担う国民づくりのための教育改革と、いわば国家のフレーム自体をつくり変える「憲法改正」とは「新しい国」づくりのための一連の課題と見ることができます。
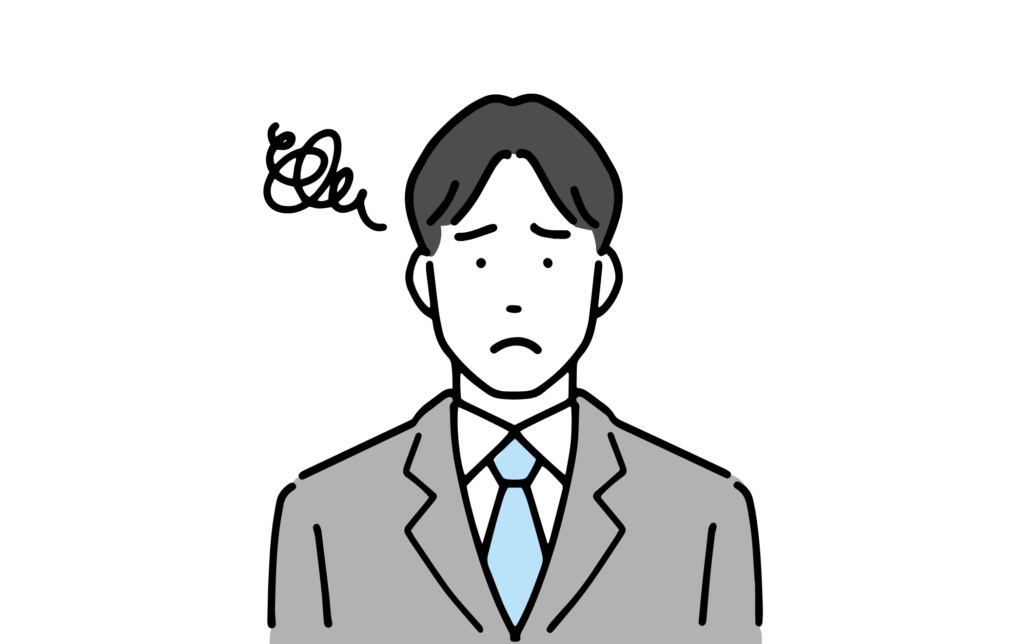
もとより、一般論としては、憲法改正が立憲主義の否定となるものではありません。
しかし、昨今の改憲論議に見る憲法改正手続き要件の緩和(憲法96条)や閣議決定による集団的自衛権の解釈変更(憲法9条)といった主張は、国家権力を制限して人権保障を図るという立憲主義の思想に、明らかに逆行するものです。
すでに自民党が野党時代に発表していた「日本国憲法改正草案」(2012年4月27日)は、基本的人権を制約できる根拠として新たに「公益及び公の秩序」(13条、21条)を置いているなど、基本的人権を制約する根拠を国家権力に与える内容となっています。それは、立憲主義の否定にほかならないのです。 (つづく)
『クレスコ 2014年8月』(大月書店)より



コメント