学校をどう変えるか(4)
N中校長への書簡④
そろえることとそろえないこと(その2)
そろえることとそろえないことについてもう少し考えてみたいと思います。
そもそも学校は、そろえるのが好きですね。
何でもそろえたがる。
「そもそも学校は」というのが違っているかもしれません。
正しくいえば「日本の学校は」でしょう。
服をそろえたがります。
ほとんどの中学校や高校では〝制服〟があります。
制服を廃止して、全く自由にしたり、選択できるようにした学校も出てきましたが、ごく一部です。
その一部のなかには、女子生徒がズボンを着用したり(これは少しずつひろがっているようです)、男子生徒がスカートを着用したりすることも可とした学校もあります。
体育で着用するジャージをそろえる。
通学バッグをそろえる。
スカートの丈の長さをそろえる。
髪を染めてはいけない。
ピアスはだめ。
持ち物もそろえます。
水筒はもってきてよいが、中身はお茶か水。
スマホはダメ。
靴下の色まで指定している学校もあるとか。
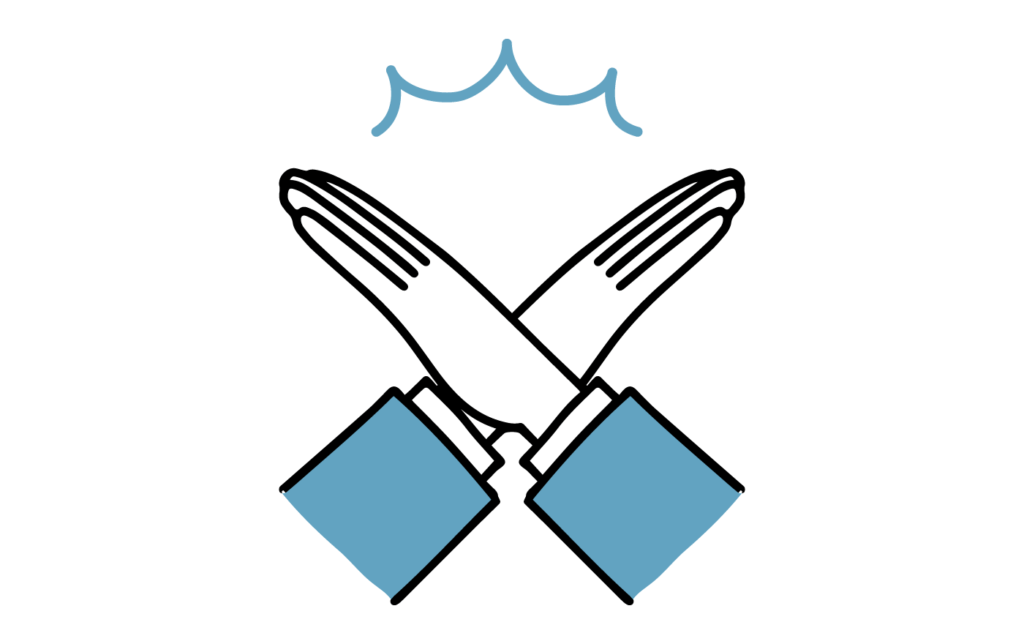
これらの〝校則〟にどれだけの意味があるのでしょうか。(スマホについては、欧米諸国でも禁止するところが増えているそうですが、それは子どもたちの成長・発達に害があることが明らかになってきたからで、これについては別に述べたいと思います。日本の学校では、スマホは不要だ、授業に集中できなくなる、という理由です)
始業式や終業式、全校集会などで並ぶとき、列をそろえます。
「たて・よこ、そろえなさい」と。
運動会・体育祭の入場行進。私の初任の学校でも、入場行進の練習をよくやらせていました。
列をそろえて行進しろ、カーブのところでは、外側の子は大股で歩け、と。
もう笑っちゃいますよね。
職員会議で「入場行進の練習に時間をかけるのはやめませんか。
競技の練習に時間をかけましょう。
グラウンドを一周するのはやめて、応援席からまっすぐ入場すればいいのではないですか」と提案しましたら、「それがいい」とすんなり通りました。
N中では、始業式や全校集会で体育館へ移動するとき〝無言入場〟、教室へ戻るとき〝無言退場〟という決まりがあります。
「一切喋ってはいけない」で、そろっています。これも全く意味がわかりません。
でも、何でもそろっている方がきれいじゃないか、美しいじゃないかと仰るかもしれません。
想起されるのが、軍隊の行進です。ヒトラー=ナチスの行進なんか、とってもカッコいい、美しい。
一方、アーティスティックスイミングや新体操で演技がそろっているのは、本当にすばらしい。
感動します。
軍隊の行進と、何が違うのでしょうか。
オリンピックの入場行進と軍隊の行進、何が違うのでしょうか。
ここのところをはっきりさせておかないといけないと思います。
戦前、子どもたちは軍隊の行進はかっこいいと思ったのでしょうから。
そろえることの、すばらしさと危険性とは、見かけは紙一重のようで、実は決定的な違いがあります。
軍隊は所詮、戦争し敵を倒し殺す集団であり、そのために一致団結させる行進です。
命令され、強制された行進です。
オリンピックは、選手一人ひとりが演技や競技の可能性に挑戦し、かつ、平和を願い、他国の選手たちとの友情を育むための行進です。
アーティスティックスイミングや新体操は、選手たちが自らの人間性を表現するもので、やらされているものではありません。
以前テレビで、たしか東京交響楽団だったと思います。
指揮は誰だったか忘れましたが、ブルックナーの交響曲第9番を演奏していました。
その第2楽章スケルツォ。
ヴァイオリンパート全員のボーイングが見事にそろっていて(もちろん音も)美しく感動的でした。
楽団員一人ひとりが自分の持てる力と熱い心で演奏している結果なのです。
私が以前いた学校では、合唱に取り組みました。
圧巻は、学年合唱でした。
からだを大きく揺らしながら歌う子、眼を輝かせて歌う子、首を振りながら歌う子、まっすぐ立って歌う子…、けっしてそろってはいません。
しかし、歌声は指揮者を起点にそろっています。
〝いい合唱にしよう!〟〝すばらしい感動をつくりあげよう!〟という心がそろっていました。
なぜ合唱なのか?
音楽という芸術がもっている力、人間性があるからです。
合唱は、やらされてできるものではないからです。
校歌を練習したことはほとんどありませんでした。
校歌は、自分たちが育った母校に愛情をもち、自分たちがつくっていったという誇りをもつならば、自然に歌いたくなるものですから。
そういう一致した心というものは、強制されて生まれるものではありません。
N中は、どうでしょうか?
〝そろい〟がホンモノかどうか、検証してみる必要があるのかもしれません。
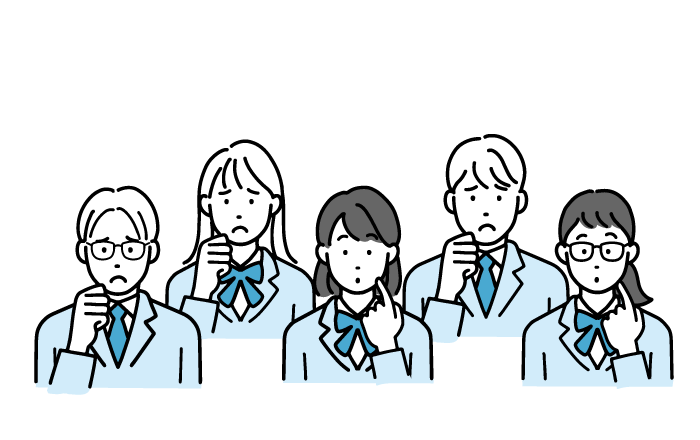
子どもたちの自主性に本当に根差した活動を粘り強く創造していくなら、子どもたちが人間性を育てていった結果としての〝そろい〟が出現するでしょう。
子どもたちがその気になれば、そんなに時間はかからないでしょう。
誰がその気にさせますか?



コメント