学校をどう変えるか(10)
新自由主義教育による競争主義
新自由主義とは、規制緩和・効率化によって公的な事業も次々に民営化をすすめ、市場原理を社会の隅々まで広げ競争を活発にすることで経済活動が活発になり、人々の生活もゆたかになる、という経済理論です。
民営化することで政府の役割は減るので、新自由主義を唱える人は「小さな政府」論を主張します。
そうすれば財政支出が減り、身軽になるというわけです。
「小さな政府」にするために、政府の財政負担の大きな部分を占める社会保障費や教育費の削減を進めました。
新自由主義の提唱者であるフリードマンは、政府の仕事は、警察と軍事ぐらいしかなくなると言いました。
大企業が儲かればその利益が滴り落ちて(トリクルダウン)労働者の賃金も上がるというわけです。
新自由主義論者は、競争によって社会が活性化し、市場の自動調整機能が働き、それによって社会が発展していく、と主張しました。
私は、新自由主義は、矛盾や綻びが顕著になってきた資本主義経済体制の生き残り戦略ではないかと見ています。
フリードマンはイギリスの経済学者ですが、新自由主義を強力に推し進めたのはイギリスのサッチャー政権、アメリカのレーガン政権。
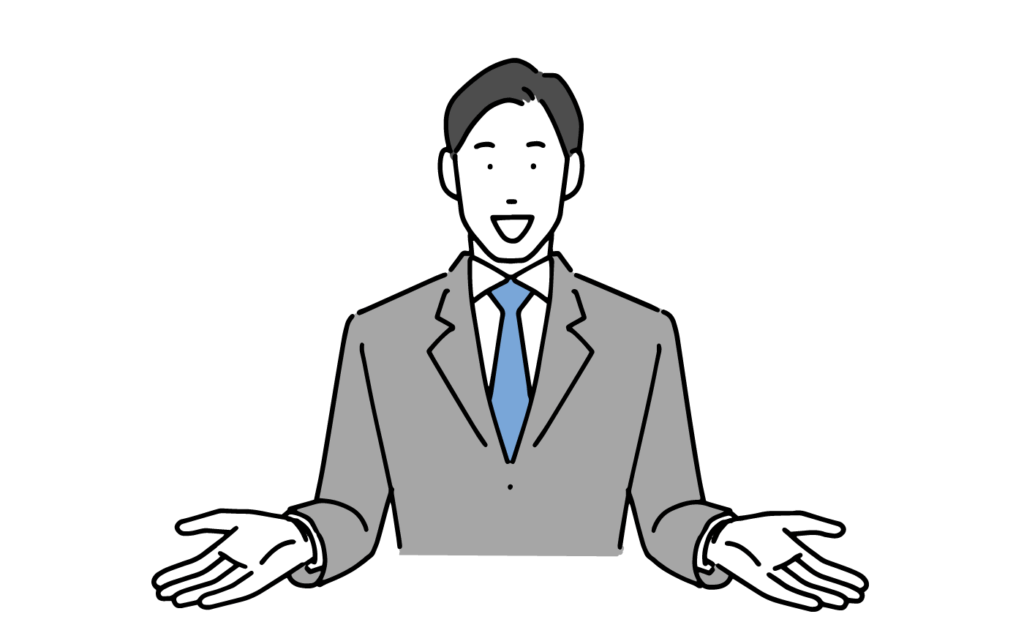
そして日本では、中曽根政権、小泉政権、です。
中曽根政権は、国鉄の民営化、たばこの民営化、電電公社の民営化を進めました。
小泉政権は、郵政民営化、道路公団の民営化を進めました。
また、小泉政権は、地方自治法を「改正」し「指定管理者制度」を導入し、地方の公的役割(図書館、公民館、音楽ホール、美術館など)の民営化を進めました。
そして、公務員を減らし、教職員の給与の総額は絶対に増やさないという方針を決めました。
それで、教職員の給与の国庫負担を2分の1から3分の1にしました。
安倍政権も新自由主義路線を強力に継承しました。
安倍氏は首相就任時に、大企業がもうけられる国にしたいと言ってはばかりませんでした。
地方自治体に会計年度任用制度を導入し、地方自治体職員の約半数が非正規雇用になりました。
教育のコストダウンのため、学校の統廃合、学校給食のセンター化を進めました。全国学力テストを始め、子どもたちを競争に追い立て、学校の序列化を進めました。
教育政策に、経済産業省を関与させ、教育は、企業に役立つ人材づくりという立場を鮮明にしました。
日本の教育政策で厄介なのは、それに、戦前の軍国主義回帰の復古主義が加わっていることです。
イギリスでもアメリカでも、新自由主義を教育・学校にまで、その触手を広げました。
サッチャー政権が、全国学力テストを実施し、イギリスでは混乱が起こって反対運動が起こり、見直しが図られたそうです。
アメリカでも全国学力テストが実施されました。
日本の新自由主義教育は、だいたいアメリカの後追いで行われているのです。
新自由主義教育で、学校はどうなったか
新自由主義で、社会保障費が削減され、その結果、富裕層と貧困層の格差が広がり、それがそのまま子どもの貧困率の増大になっています。
日本の貧困率は、アメリカと1位2位を競っている状況です。
子どもの貧困率は9人に1人。
経済格差が、文化格差、学力格差につながっています。
新自由主義では、競争させることが目的になり、勝つことが至上命令になります。
弱肉強食の苛烈な、生きるか死ぬかの戦いです。
勝ち組と負け組が生まれるのは織り込み済みのことです。
競争によって子どもたちはストレスを抱え、健全な成長発達に歪みが生じ、不登校は増え、いじめが後を絶ちません。
教育が商品化され、塾、教材など教育産業が利益追求の重要分野となっています。
文部科学省の教育課程審議会の会長をつとめたM氏は、学力テストには賛成、できない子はできないままでいい、3分の子がわかればいい、と言い放ちました。
教育に、競争と勝ち負けはなじみません。
私たちは、すべての子どもに自立の力につながる学力を身に付けさせたい。
そのために、すべての子どもに理性と知性を育て、感性を磨かせたい。
みんなで力を合わせ、助け合い励まし合って、人間らしい文化芸術を創造し、感動を味わわせたいと願うからです。
共同を築く手段としての競い合い
私が以前勤めた中学校では、1学期は、1年遠足、2年キャンプ、3年修学旅行。
2学期は、9月に体育祭、10月か11月に合唱祭(12月の年もありました)。
3学期は、3年生を送る会、卒業式。
そのうち体育祭と合唱祭は、クラス対抗、ブロック(縦割りクラス)対抗です。
競い合いです。
各クラスが「優勝したい!」「最優秀賞をとりたい!」「金賞をとりたい!」と燃えます。
なあんだ、いまどこの学校でも、運動会や合唱コンクールで競争させてるじゃないか!
そう短絡的に考えてはいけません。
その「競争」の意味をもう少し深く考えてみましょう。
みごと優勝したクラスがあります。
みごと金賞に輝いたクラスもあります。
「やったあ!」と喜び合います。
賞状をもらえたことに満面の笑顔で、クラスみんなで素直に喜びます。
しかし、同時に賞状の紙を超えたものがあることに気付きます。
いくつものもめごと、トラブルを乗り越えみんなで築き上げたことに感動します。
一方、賞を取れなかったクラスは、取れたクラスにたいして素直にあたたかい拍手をおくり、讃えます。
そのクラスも、いくつものトラブルやもめごとを乗り越えてきたのです。
賞を取れたクラスは、取れなかったクラスの健闘を讃えます。
どのクラスもやりきった達成感に浸ります。
勝ち負けを超えたものを生み出したのです。
全校に友情と信頼が広がるのです。
全校が人間のあたたかさで満たされます。

オリンピックなどのスポーツ大会もそうです。
激しい競い合いです。
しかしこれも、ゲームです。
gameの語源は、「楽しみ→遊び」だそうです。
敗者は勝者を讃え、勝者もまた敗者を讃えます。
オリンピックなどでもよく目にする光景です。
そこに友情が芽生え、平和を願う心が通います。
これは、新自由主義による競争とはまったく別物です。
前回まで紹介したフィンランドは、アメリカ型の新自由主義教育とは真逆の教育政策を進めています。
フィンランドでは、何よりも平等を大事にし、すべての子どもが人間らしく育つように、教育のシステムができています。
政府が、福祉や教育に手厚くお金を出します。
フィンランドは、日本から6・3制のシステムを学んだそうです。
いまは、日本がフィンランドから学ぶことが多そうですね。



コメント