学校をどう変えるか(16)
M中の不思議・その6
競争主義、点数主義は、学習の動機にはならない!?
どうやらM中は、効率と競争、教育の場に市場原理を持ち込ませた新自由主義教育にどっぷり浸かってしまっているようです。
先生方も生徒たちも、異常にテストの点数に拘ります。
各学期の始業式に、各学年の代表が、つまり1年生から3年生まで一人ずつ、「今学期の抱負」を述べるコーナーがあります。
それ自体は、よいことだと思います。
自分で書いた作文読み上げます。
それぞれ、今学期がんばりたいことを述べるのですが、3人とも「勉強をがんばりたい」と言います。
共通なのが、「テストの点数を上げたい!」。
素直な気持ちでしょう。
「理科の○○について興味があるので、もっと勉強したい」「英語が好きなので、会話もできるようにしたい」「歴史に興味があるので、もっと深く勉強したい」…というような発言はありません。
学期ごとに抱負を述べるので、もう5回ほど聞いているのですが、毎回どの子も「テストの点数」を言うだけです。
私は、定期テストの問題をつくりますが、子どもたちに「授業でやったこと、ノートにまとめてあることから問題を出します」と前もって言います。
社会科の基礎的知識を身に付けさせたいからです。

ですから、そんなに難しい問題ではありません。
前任校も、決して学力は高い学校ではなかったのですが、平均点が70点を(100点満点)下回ることはありませんでした。
しかし、M中では驚きました。
平均点が50点台半ば、50点を切るクラスもあります。
平均点というものが意味があるとは思いませんし、学力とは何かを問わなければならないとは思いますが、こんなに低いのは経験がありません。
すごい格差が起こっているのです。
80点以上の子もそこそこいるのですが、10点台、20点台の子が異常に多いのです。
わかったことは、「点数、点数」と異常に気にしながら(各教科の点数も気にしますし、5教科の合計点も気にします。
先生方が合計点を意識させているのではないかと思います)、点数が取れない。
点数競争に追い立てられ、その競争に乗れない子が多いのではないか、ということです。
子どもたちは、点数を気にしながら、「勉強は好きか?」と訊くと、ほとんどの子が「嫌い!」とこたえます。
「学校は好きか?」と訊くと、ほとんどの子が「嫌い!」とこたえます。
点数競争で「勝ち組になりたい」「負け組になりたくない」と思いながら、それが勉強する意欲にはなっていないのではないでしょうか。
授業中M中の子どもたちを見ていると、授業の中身ついて、「なるほど、そうなっていたのか」「それはスゴイ」…という反応を示し、わかる喜び、知る楽しさを感じている子が、ごく少数いるようです(これをAグループと呼びましょう)。この子たちは、意欲的に学習に取り組んでいるので、その結果としてテストの点数もよくなります。
そこまでの意識はないものの、「授業はまじめに集中してやらなくちゃ」という子が一定人数いるようです(これをBグループと呼びましょう)。
私は、2年生1クラス、1年生2クラス、授業を受け持っていますが、2年生は、ここまでの子がクラスの多数を占めているようです。
そして、おそらく勉強にたいする苦手意識が強くなかなか意欲が高まらない子がいるようです(これをCグループと呼びましょう)。しかし2年生は、AグループやBグループに引っ張られて、Cグループの子たちの中に、一所懸命にやろうという意欲が現れてきています。
授業の中で、学級集団の中に、助け合い励まし合い学び合う関係を築いていくことが、私自身の課題だと考えています。
学級担任も班編成や班長への指導などで意識的に学級づくりに取り組んでいるのかもしれません。
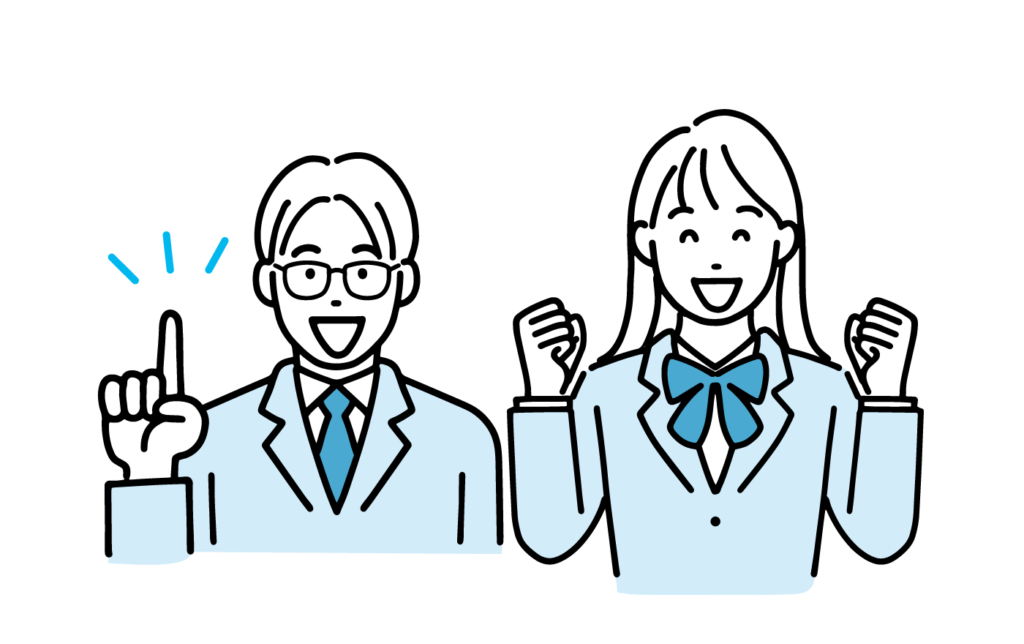
1年生の状況は、深刻だと思います。
Aグループ、Bグループの子たちは一定いるのですが、はじめから気持ちを勉強に向けようとしない子があまりにも多い。
授業の中で、そこをどう変えていくのかが、私自身の課題です。
私は学級づくりの中で、授業に集中するためにどう班をつくり、班長がどんな役割を果たすかということに取り組んできましたが、そういう学級づくりの視点は見えません。
社会科の授業のなかで活路を見出していくしかないと考えています。
いずれにしても、大都市圏の一部の富裕層の中には、〝いい高校〟→〝いい大学〟→〝いい会社又は、高級官吏〟という〝エリート〟路線にしっかり乗っていこうという指向もあるでしょうが、
いま私が勤めている所は、そういう地域では全くありません。
それなのに、子どもたちは〝点数競争〟に追い立てられているように見えます。
〝点数〟は、学習する意欲をうみだすのでしょうか。
私は否と思います。学力とは何か? 学ぶとは何か? 問い直し、学ぶ喜び、知る楽しさ、わかる感動が生まれる授業づくり、学級づくりを追究していかなければと考えています。
M中は、先生方も生徒もテストの点数を異常に気にします。
全国学力テストを実施し、その結果を分析※してどう生かすかに一生懸命です。
3年生になると、高校入試に向けて、〝総合テスト〟〝業者テスト※〟。
適性検査※、心理テスト※。
定期テストの3週間前なると、〝テスト範囲〟を発表し、テストに向けた学習計画を立てさせます。
国・社・数・理・英の各教科のワーク(問題集)※を1年生~3年生まで、全員購入させられます。
3年生は、それ+「新研究」という名の分厚い問題集※を購入させられます。
夏休みや冬休みには、5教科の入った問題集※を購入させられ、宿題になります。
3年生は、さらに高校入試の〝模擬テスト〟※を購入させられます。
※は、業者から購入する物やサービスです。
私には、テスト、問題集の〝洪水〟に見えます。
私には、異常に見えます。
新自由主義教育とは、教育の場に市場原理を導入し(教育を商品化し儲けの対象にする)、
子どもたちを競争主義・点数主義に追い込み、学校の序列化をすすめ、教職員と子どもたちを分断し(「個別最適化」と称しています)、格差を広げるものです。

イギリスのサッチャー政権、アメリカのレーガン政権から始まり、日本では中曽根政権から始まりました。
日本では、とくにアメリカでやったことを後追い的にやってきました。
イギリスやアメリカでは、「新自由主義教育は間違っていた」と見直しが始まっています。
日本でも、当初から批判が強かったものの、全国学力テストやGIGAスクール構想、「道徳」の教科化などが強行されています。
加えて、教育委員会制度の改革(改悪)、教科書採択制度の改革(改悪)などで国による統制が強化されています。
M中は、新自由主義教育のオンパレードではないか?!
私は、おかしさとともに、大変な怖さを感じます。
先生方は〝善人〟なのです。「善かれ」と思って、やっていらっしゃる。
〝良いことだ〟と思ってやっていらっしゃる。
しかし、これでは子どもは育たない!
人間の自立に必要な理性と知性と感性は育たない。
人間らしいゆたかな心は育たない。
私はそう思います。
子どもたちは、「自由」の中にいるようで、実は不自由の檻の中に閉じ込められているのではないか?
そんな気がします。



コメント