クラスづくりの展望② ~1年間を見通して~
中庸を行け!
私は、教師2年目=クラス担任2年目に大失敗をしました。(この年のことは、後述するつもりです)
その時、同じ職場で多くのことを教えていただいたY先生(私が生涯尊敬する先生となりました)に、助言をいただきました
そのY先生から聞いた話。
先生たちがやっているクラスづくりをよく見てごらん。
だいたい、2つのタイプがあることがわかると思うよ。
A:一つは、先生がグイグイ引っ張っていくタイプ。比喩的にいうと、子どもたちを全部自分の掌に載せちゃおうというタイプだ。管理主義。「オレについてこい!文句は言うな!」。別の言い方をすると、アメとムチ方式。

強烈な先生は、これをやりきっちゃうから、凄い。でも、きちんとしているから、授業では私語がない。上手い先生は、暴力を振るうのでもなく、子どもたちへの当たりもソフトで信頼もある。統率がとれているから、他の先生たちから「きちんとしている」と褒められる。それで、体育祭や合唱祭でも優勝する。見栄えがいいから、他からも褒められる。そういうクラス、あるでしょ。
B:もう一つは、子どもの声を大事にしようと思っている。しかし、子どもを中心にしようと、最初から子どもたちに「自分たちで自由にやっていいよ」と任せてしまう。放任主義。そのあまり、子どもたちに先生が引きずられてしまう。

「席は、好きな子同士がいい!」「先生、弁当食べる時、自由な席がいい!」と言われ、「じゃあ、そうしましょう」と。
そういうクラスも、あるでしょ。
これは、子どもの声を聞いているようで、教師の指導性が欠如しているので、私語が多くだらしないクラスになってしまう危険性がある。あまりにもだらしなくなると、突然先生が「コラー!」と怒り出す。子どもは、「何を突然!」と面食らう。
授業に行く先生は、非常にやりにくい。だから、前者の方がよく見えてしまう。
前者は、きちんとしているが、子どもたちの声・意見を大事にするという民主主義の視点が欠けている。「きちんと」主義。取り締まりになってしまう。子どもをどう育てるかという視点がない。上手くやれば、マインドコントロール。教育じゃない。
後者は、子どもの意見を聞こうとするが、無秩序に陥る。子どもをどう育てていくかという思想が薄弱。教師の指導性が欠けている。これも教育とはいえない。
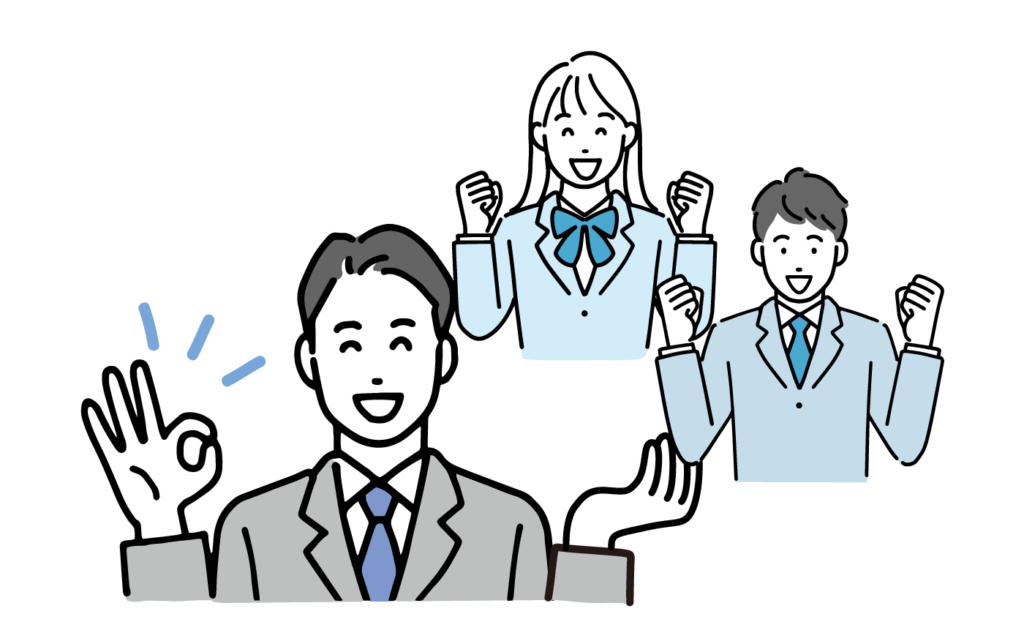
秩序を保つために必要な管理をしながら、同時に子どもの声を尊重して民主的なクラスを築いていくという思想が必要じゃないだろうか。
AとBの中庸を行くということかな。
というわけで、前回述べたように、初めは教師が管理し、子どもたちがそこから自由・自治を勝ちとっていくという手法がいいのではないかと考えるのです。



コメント