「建国記念の日」ってどんな日?
2月11日は「建国記念の日」。1967年、祝日になりました。
昔は、紀元節といいました。どんな日なのでしょうか。
科学的根拠はまったくない
神話上、天皇家の先祖といわれる神武天皇即位の日とされるこの日を祝うのが紀元節です。
1873年(明治6年)に制定されたのですが、科学的根拠はまったくありません。
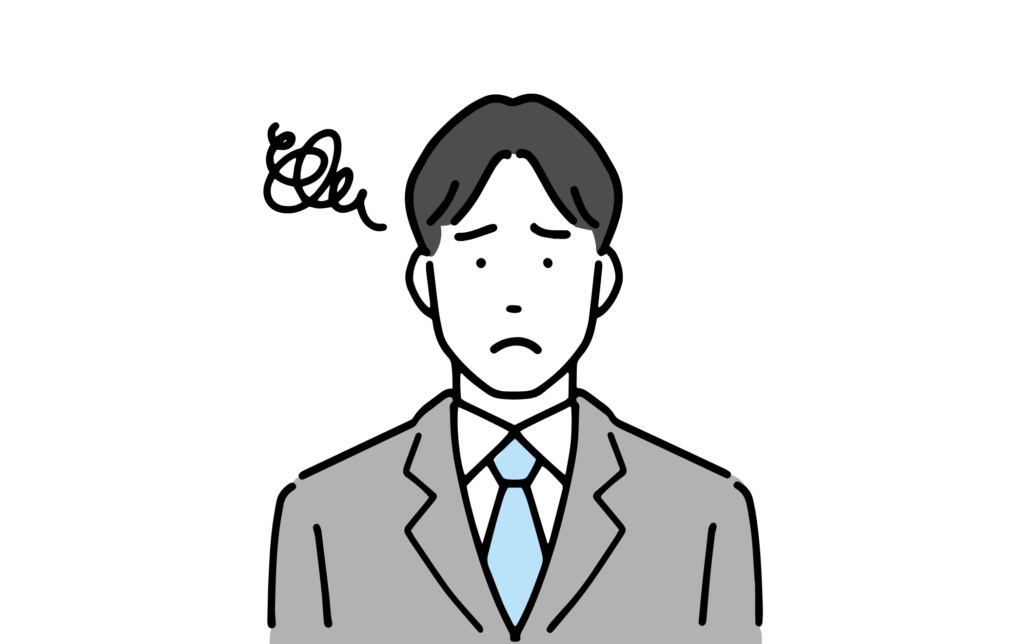
制定にあたって根拠にしたのが、「日本書紀」の記述。
西暦になおすと、紀元前660年といいますから、狩猟・採集、平均寿命30歳の縄文時代です。
神武天皇の死んだ年齢は、「古事記」では137歳、「日本書紀」では127歳となっています。
日本で小国家が生まれるのは、弥生時代です。
神武天皇が存在しなかったことは、明白な歴史的事実です。
2月11日を利用して
紀元節は、民衆にとっては節句などと違って、なじみのうすいものでした。
1889年、明治政府は紀元節に合わせて大日本帝国憲法を発布します。
高村光太郎の「暗愚小伝」によれば、その日は雪が降り、上野に出かけた光太郎は、騎兵を先頭にした天皇の馬車を見ます。
すると、突然「目がつぶれるぞ」という声とともに土下座させられ顔を雪の中につっこまれます。
砂が口に入ったそうです。
明治憲法の発布や紀元節というものが、いかに国民にとって強圧的なものであったか、知ることができると思います。

15年戦争中は、紀元節を節目に、「どこどこの国のここを占領せよ」という無謀な計画が至上命令としてありました。
それによって、どれだけ無駄に人命が失われたか……。
だれが、なぜ復活させたか
戦後、紀元節が新しい国民の祝日にならなかったのは当然です。
しかし、戦前と同じ状況を復活させたいという動きが、紀元節復活の動きとして起こったのです。
軍国主義復活に国民を巻き込むために、2月11日を利用しようとする動きがあります。
昨年、文部科学省の検定を通過した令和書籍の中学校社会科用『国史教科書』は、建国神話を大々的に取り上げています。
昨年7月、政府は内閣官房に「昭和100年関連施設推進室」を設置し、12月には関連施策関係府省連絡会議の初会合を開きました。
戦争と植民地支配にたいする反省がないことが気掛かりです。
戦後の平和と民主主義を守り発展させる運動をこそ、幅広い国民の年中行事にしていくことが大事だと思います。
(参考:加藤文三「紀元節ってなに?」 大日向純夫「戦後80年の『建国記念の日』」)



コメント