教育の目的(7) 自立の力を育てる
自立とは、もうひとりの自分を育てることだと述べてきました。
そして、それは自己中心性を抜けきり、自分の中に理性と知性を育むことだと述べてきました。
その土台となる普遍的な価値観を身につける必要があります。
このブログのはじめの頃に書いた「教育の3つ規範」に立ち戻ることになりますが、それは人権尊重と民主主義の理念です。(特定の価値観を押しけることではありません)
「これからどう生きていくか」という重大な岐路に立ったときに、身につけた理性と知性を総動員して決断しなければならない、という時もくるでしょう。
いや、そうでなくても、「これからどう生きていくか」という問題は、きわめて日常的なことで、大袈裟なことではないのかもしれません。なぜなら、「きょうはどうだったか、明日はどう生きていくか」の毎日ですから。
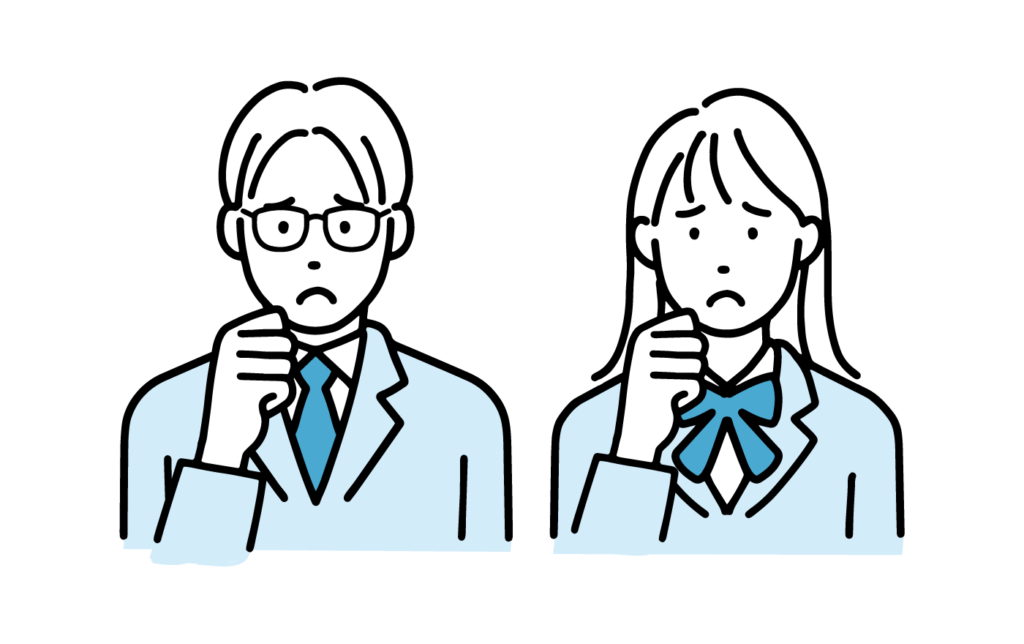
毎日の自己内対話で、「明日はどう生きていくか」自分で判断していく。毎日毎日が自立の階段を昇っていく訓練場です。階段を踏み外したり、昇りきれなかったりすることもしばしば。過ちや失敗は織り込み済みです。悩み迷うことも織り込み済み。過ちや失敗、悩み、迷いが多いほど、成長するともいえます。それだけ、もうひとりの自分を鍛えられますから。まだまだ学習が足りないと気付きますから。その意味で中学校の9教科は、理にかなっていると思います。どの教科も欠かせません。
おとなでさえ、自立が難しい世の中です。まして、子どもはなおさらです。
こう述べてきた私自身、悩み迷う日々です。まだまだ知るべきことを知らない、と思い知らされる毎日です。(〝知〟の問題は、項を改めて述べるつもりです)
SNSの広がりで情報過多の状況になっている今日、何が真実か、何が本質かを見極める力が求められています。(兵庫県知事のパワハラ問題から始まった、あの混乱は何なのでしょうか?)メディアリテラシーを育てることは学校教育においてきわめて重要だと思います。
学校のクラス活動の中で、些細なことかもしれませんが、問題やもめ事が起こります。班で、クラスで討議することによって、もうひとりの自分が登場する場面が増えます。暴力・いじめなど大きな問題が起これば(もちろん、起こらないに越したことはありませんが)、実践的な教育の大きなチャンスでもあります(いじめ問題の取り組みの項で、述べたとおりです)。
「司会係の3班に要求があります。帰りの会を始めるのが遅いので早くしてください!」
要求された3班は応えなければなりません。「何言ってるんだよ、そんことねーよ!」と感情的になってはいけません。理性的になって、なぜ遅くなったのか? 3班が原因なのか? 教室掃除の終わるのが遅かったからではないのか? 知性を働かせ、班会議して事実を確認し、回答しなければなりません。非があれば、謝罪し、改善を図ればいいのです。
学校において、学級において、相互評価することと相互批判することは不可欠です。

理性と知性を育てることは、一筋縄では行きません。
9教科の学習と、学級・学年・全校の活動の中で、育っていくものでしょう。
教育の目的は、一人ひとりの〝自立の力〟を育てることだと、私は考えています。そのための理性と知性と感性を育むこと、及び、その土台となる人権尊重と民主主義の理念を実践的に教えることだと考えています。それは、集団の中でこそ育ちます。(「テストの点を取るため」とか、「高校へ進学するため」ではないでしょう。)
そのために学校で身につける力が〝学力〟ではないでしょうか。(「学力」については、項を改めて述べたいと思います)。
これは、私の考えなので、異論があっても当然です。議論することが大事です。
※「理性」を育てるのに必要な教科の中に入れしまいましたが、音楽や美術は厳密にいえば、人間らしい「感性」を育てるものでしょう。料理のスパイスのようなもので、ゆたかな人間らしい感性も必要です。(どう分類するかは、ここではそれほど重要ではないでしょう。)
※※付言すれば、「道徳」が教科化され、現場では混乱も生じているようです。
私は、学校現場に必要なのは「道徳」ではなく、「哲学」だと考えています。(映画「ぼくたちの哲学教室」は大変示唆に富んでいます)



コメント