教育の目的(9) 自立の力を育てる
問われる大人・教師の自立
1947年教育基本法では、次のように定めています。
第1条[教育の目的]
教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。
「人格の完成」とは、自立の力を身につけるということに他ならないことが明らかになりました。
教育の全ての活動が、この目的めざして修練されなければなりません。
理性と知性を育て、他人に支配されることなく、自己内対話を続け、何が正しいか自分のアタマで考え、「これこそホントウだ」と見極め判断する。前述したように、間違いや失敗も織り込み済み。
だが、どこかで「これは間違っていた」「自分は無知だった」と気付かなくてはならない。
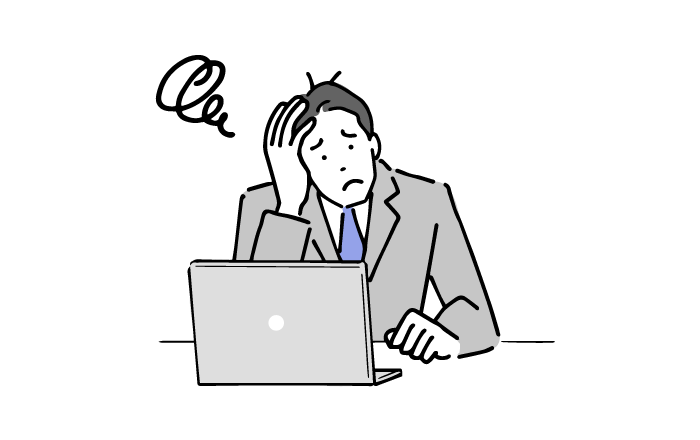
と、考えると、〝自立〟は、そう簡単にできることではありません。
思い込みや偏見、先入観、固定観念は、自立を阻みます。
子どもたちに、自立の力を育てるには、まずなにより、育てる側の大人・教師が、思い込みや偏見、先入観、固定観念からフリー自由になって、勉強し考えぬくことができなければなりません。
「あなたは、人格が完成していますか?」と問われ、「はい」とこたえられる人は何人いるでしょうか。
と、考えると、自分にそんな人格がそなわっているのだろうか、と自信を失いそうです。
その謙虚さが必要です。
私は、子どもたちとともに、子どもたちから学びながら、自分も育っていくものだと悟りました。
私自身、知らないことが多過ぎて、もうすぐ70歳だというのに、いまだ発達途上です。
この中途半端さも必要でしょう。
「あれは正しかったのだろうか?」と考えることが数多くあります。
ただ、いままで述べてきたように、子どもは集団の中でこそ育つ、議論し評価し合ったり批判し合ったりするなかで育つ、といったことは、確信にまで至った理念です。
大人自身も、教師自身も、間違いや失敗を繰り返しながら、本を読み思索を深め、行きつ戻りつ悩み迷いながらも、らせん階段を一歩一歩昇っていくってことでしょうか。
それって、ホントウに正しいですか?
いくつかの例をあげて、考えてみましょう。
その一つ。
私は、〝子どもは集団の中でこそ育つ〟という確信から、いままで述べてきたように、自立の力を育てるために、クラスづくりが重要だと考えています。
そのために、3つの要素があります。リーダーを育てることと、班をつくり班で活動すること、討議をすること。これも三十数年やってきて、一つの結論です。
おそらく、どこの中学校でも、班があり、班長がいて、学級会という討議の場があるでしょう。
(全国の中学校を調査したわけではないので、ない学校もあるかもしれません。ごく小規模の学校では、全校集団がその集団にあたります)
学級づくりにとって、班長(リーダー)をどう選ぶか、班をどう編成するか、討議をどうつくるかは、決定的に重要です。
学級を自立する集団に育てるために、班長は立候補で選ぶ、班は自治的に生活する集団から学習する集団に発展させることを意図して編成する、小さな討議を積み重ねて討議する力を育てる、という手法がどうしても必要になります。
学級づくりの発展過程で、班の編成替え(班替え)が必要になります。もちろん、これも子どもたちが討議して自分たちで決めることが大事です。
ところが、見聞きするほとんどの学校で、班の編成替えではなく、席替えなのです。それもくじ引きで。それが当たり前のように。
学級という集団を、子どもたち自身が、〝こう変えよう〟〝こんなクラスにしよう〟〝こんなことができるクラスにしよう〟という目的意識がもって、そのためにどうしようと討議することが必要だと私は考えるのですが…。

くじ引きで席替えして、何を育てたいのか、見えてこないのです。
私がやってきたことが間違っていたのか? 自己内対話をしたのですが、子どもたちが自分で考え判断する、自立の力が育っていったという実感があるもので、「おまえがやってきたことは間違っていないと思うよ」というコタエが返ってきます。
もしかしたら、先生たちが、席替えをくじ引きでやることが当たり前だという固定観念にとらわれていないでしょうか。失礼な言い方になって恐縮しますが、子どもを育てるために、こんな学級づくりの思想と手法があることを知らない? 知らないことを知らない?
で、このブログを綴っているのですが…。
学級解体論まで囁かれている昨今、子どもを育てるためにクラスづくりは不可欠。
老婆心ながら囁いております。



コメント