教育の目的(12)
自立の力を育てる
理性と知性と感性に裏打ちされた自立の、ひとつの姿
オーケストラの演奏に見る自立した文化 ~理性と知性と感性の統一体~
このところ、人間の自立と教育の目的について、ずっと考えています。
理性と知性を育て、感性を磨き、他に支配されず自分で何が正しいか、何が本当か真実かを見極め、判断し、生きていけたらいいですね。
こういうことを考えている時、たまたまNHKEテレで、ファビオ・ルイージ指揮、NHK交響楽団、ムソルグスキー作曲・ラヴェル編曲「展覧会の絵」の演奏を見ました(聴きました)。
指揮者は、指揮台にすっくと立って、表情豊かにからだ全体で指揮し、自分の世界をつくっています。
音楽をつくり出すには、まず、理性の力、科学的・理論的な力が必要です。指揮者に要求されるのはまずこの力です。
音程をぴったり合わせる。
この曲にはどんなテンポがいいか決める。
指揮者は、音程の少しの狂いも聴き逃しません。
メトロノームをからだに持っています。
こんな音色がほしい、こんなフレーズ感にしてほしいと各楽器に要求します。
バランスを聴き分けます。
ムソルグスキーがこの曲をどんな経緯で作曲したか調べます。
ムソルグスキーの原曲がどんな曲かピアノ譜を勉強します。
それをラヴェルがどう編曲したか、スコアを勉強します。
気持ちを高めるところと抑えるところがあります。
感性が問われます。
楽団員一人ひとり、自分の楽器を少しの音の狂いもなく、表情をつけて奏でます。
指揮者の指示を理解して、音を出します。
他の楽器、曲ぜんたいの音を聴きながら、その中で自分の楽器のバランスを聴きます。
ソロの部分は、たっぷり歌います。
わからない点があれば、指揮者に質問もします。
指揮者に意見することもあります。
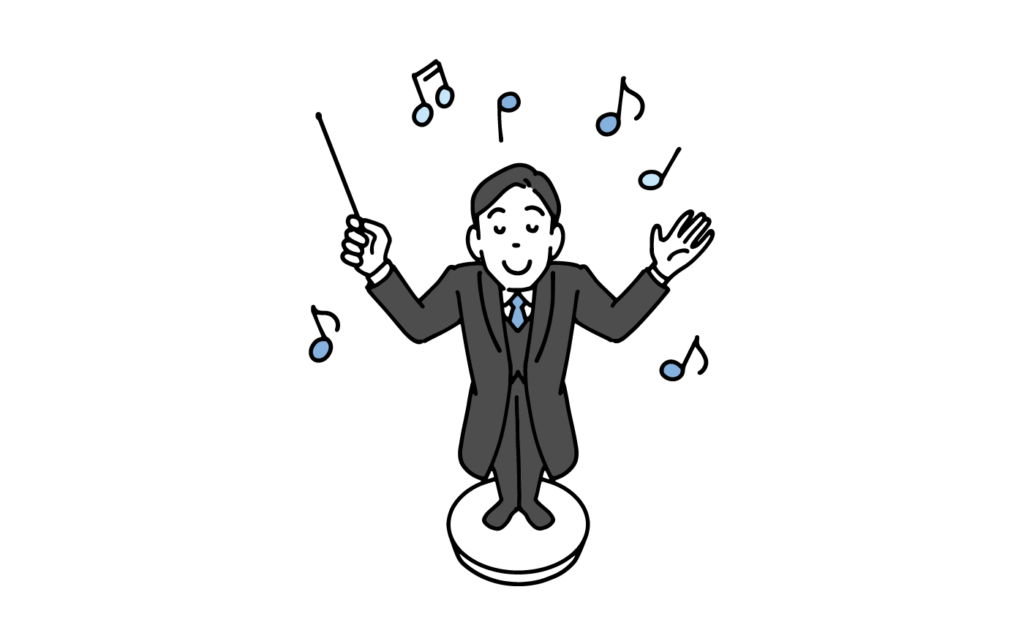
指揮者も楽団員一人ひとりも、確固たる自分をもち、自立しています。
それでいて、みごとな調和を創り出しています。
指揮者と楽団員全員でつくる共同作品です。
一体感がある中で、一人ひとりの個性が輝いています。
「青のジャンプ」を歌いきった3年1組
自立へのらせん階段は、〝ここでゴール!〟というものがあるわけでないので、一つの〝通過点〟として自立の美しさをみせてくれることが一年間のクラスづくりの中で、ほんの何回かありました。
前にも紹介した、四部合唱「青のジャンプ」を歌いきった3年1組もその一つです。
自分たちでこの曲を合唱祭で歌うことを決め、指導部をつくり、自分たちで練習に取り組んだのです。
いくつかの困難を乗り越え、子どもたち一人ひとりが自分と対話し、クラスの合唱をつくることに心を注ぎ、互いに声をかけあいました。
時には、ケンカになりそうになりながら。
この合唱をつくりあげた時は、自立へのらせん階段を一気に何段も上がったと実感しました。

本番直前、リーダーの一人Yさんが発した言葉は忘れられません。
おそらく、自分の予想を超えて、クラスが集団として成し遂げたことに心震えわせて、こう言ったのです。
「うちのクラス、ヤバい!!」



コメント