子どもの自立を阻むもの①
子どもの権利条約が蔑ろにされている
子どもの権利条約が、1989年11月20日国連総会で採択されました。20世紀末の時点での子どもの権利の世界標準を定めたものです。日本は、1990年9月21日109番目に署名し、1994年4月22日158番目に批准し、同年5月22日に発効しました。
☆差別の禁止 子どもは、人種・性・言語・宗教・政治的意見・社会的身分・出生・心身障害などにかかわらず、いかなる差別もされない。( (第2条)
- 子どもの最善の利益 子どもがかかわるすべての活動において、子どもの利益が第一に考えられなければならない。(第3条)
- 生命への権利、生存・発達の確保 すべての子どもは、生きる権利、成長し発達する権利をもっている。(第6条)
- 意見表明権 子どもは、自分に影響を及ぼすすべてのことについて、自由に自分の意見を表明する権利をもっている。(第12条)
など、子どもに保障すべき権利が定められています。(全54条)
昨年は、子どもの権利条約を日本が批准して30年の節目の年でした。
「教育の憲法」とよばれた1947年の教育基本が改正されてしまった今日、子どもの権利条約は、まさしく〝教育の憲法〟たる役割を担っているといえるでしょう。
私は、「子どもの権利条約をすすめる会」が発効した「ポケット版 子どもの権利ノート」を常にバッグに入れています。(この小冊子には、日本国憲法、ユネスコ学習権宣言、1947教育基本法も収められています)
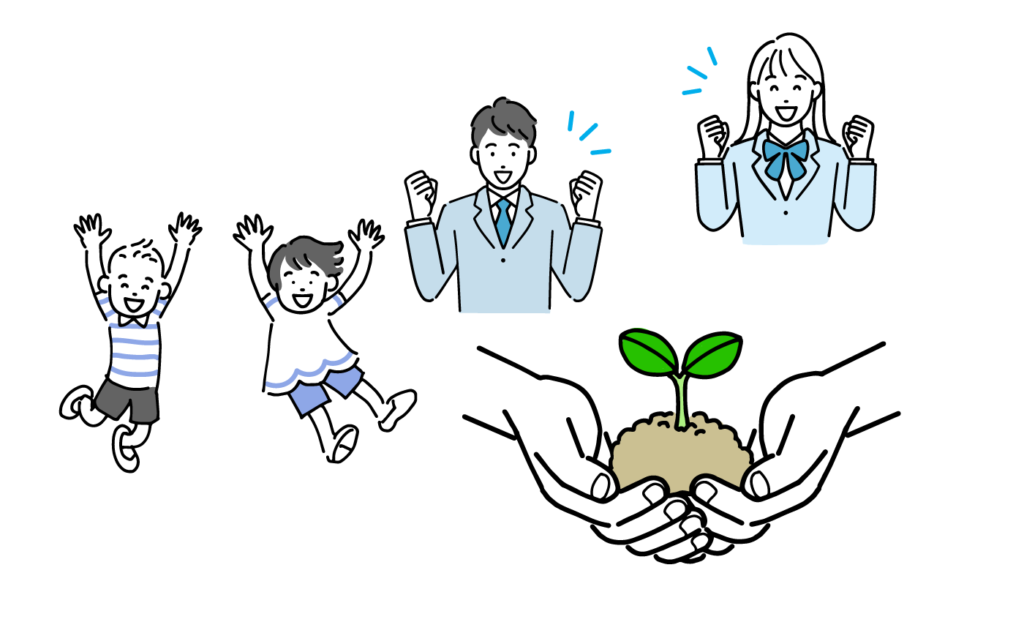
私は、1978年から公立中学校で教職に就いていましたが、1947教育基本法について、私の記憶では、国からこれを守りましょうという一片の印刷物も来ませんでした。そして、1994年子どもの権利条約が批准された時には、この重要な条約が法的に尊重される時が来たと小躍りしたものですが、国からはこの条約を尊重して子どもの権利を守りましょうという一片の印刷物も来ませんでした。
国連の活動のすぐれていることの一つは、条約を批准した国にたいして、その条約がどのくらい履行されているか調査し、良い点は評価し、改善点があれば「勧告」を出すことです。
子どもの権利条約については、5年ごとに政府が履行状況を国連子どもの権利委員会に提出し、それにたいして同委員会が、日本の状況について調査・検証し、「総括所見」を発表しています。
2019年3月に国連子どもの権利委員会が発表した「日本の第4回・第5回統合定期報告書に関する総括所見」を見てみましょう。
まず、2018年の民法改正で、最低婚姻年齢を男女とも18歳としたこと、2017年の刑法改正、2016年の児童福祉法改正、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の改正などを歓迎するとしました。
一方、多岐にわたって「懸念」「勧告」を述べています。
おもなものを挙げてみます。
国連子どもの権利委員会が、日本政府に対して「懸念」「勧告」を表明したことから。
- 子どもが、社会の競争的性質によって子ども時代および発達を害されることなく子ども時代を享受できる措置をとること。
ストレスの多い学校環境(過度に競争的なシステムを含む)から子どもを解放するための措置を強化すること。
(日本には、欧米諸国には無い高校受験制度がいまだに残っています。また、いわゆる全国学力テストが復活し、点数主義・競争主義の教育がはびこっています。) - 学校におけるいじめを防止するための反いじめプログラム及びキャンペーンを実施すること。
(日本では、いまだにいじめ事件が跡を絶ちません) - 子どもの自殺の根本原因について調査研究を行い、防止措置を実施すること。
(日本は、世界のなかでも子どもの自殺がたいへん多い国になっています) - 自己に関わるあらゆる事柄について自由に意見を表明する子どもの権利が尊重されていないことを依然として深刻に懸念する。
- 意見を形成することのできるすべて子どもにたいして、年齢制限を設けることなく、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を保障し、その意見が正当に重視されること。
(校則、ゼロトレランスに見られるように、日本は、子どもが意見を言えない、子どもの意見が反映されないこと多いのです。ドイツの中学校では、学校のカリキュラム編成にも生徒の意見が反映されるそうです) - 休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活及び芸術にたいする子どもの権利を保障する努力を強化すること。
(日本は、子どものうちに質の高い文化芸術に触れる機会が少ないのです) - 体罰を、いかに軽いものであっても、法律で明示的、全面的に禁止すること。
(日本では、体罰事件が跡を絶ちません)
国連子ども権利委員会に指摘されるまでもなくわかっていることでしょうが、世界のなかでもこの国がいかに子どもの権利が大切されていないのか、改めて認識し自覚しないわけにはいきません。
学校現場で、「憲法」「子どもの権利条約」がどれだけキーワードになっているでしょうか。
子どもは、子どもの権利条約で保障された権利の行使者・主人公です。子どもが主権者にならずに、自立の力を育てることはできません。

条約は、法律以上に法的意味が重いものです。
憲法は、最高法規です。
あなたは、子ども権利を守り育てる側にいますか?
子どもの権利を蔑ろにしていませんか?
と言われると、
私自身、ドキッとします。
学校と教職員が、憲法と子どもの権利条約を蔑ろにする教育政策に抗い、真に子どもを守り育てる立場に立ちきることが今こそ大切ではないでしょうか。



コメント