自立の力を阻むもの⑤
よかれと思ってしたことが…
最近たいへん危惧していることがあります。
中学3年生にとっては、高校進学が目の前の一大事です。
ほぼ100%の子が高校進学するようになりました。
高校進学できない少数者にならない競争は、子どもたちに大きなプレッシャーとなっているのではないでしょうか。
私が公立中学校に勤め始めた1970~80年代は、中学を卒業後就職した生徒がクラスに1人か2人いました。
90年代にはほぼ全員高校に進学するようになりました。
70~80年代は生徒急増期で、私がいた神奈川県でも高校が足りなくなり、高校の増設を求める保護者の団体ができ、署名運動が起こり、県知事が「高校100校増設」を打ち出す事態となりました。

その後、都道府県の多くが、公立高校の学区を拡大するか、学区そのものを廃止し全県1区制にしました。
そうなると、いわゆる〝名門〟といわれる公立高校をめざす生徒が増えることになります。
〝名門〟校の競争率が高くなる一方、少子化に伴い定員割れする高校が増える、という状況が生まれています。
2000年代になると、少子化に伴い、高校の統廃合が進められているのは周知の事実でしょう。
各都道府県は、中学卒業者の何パーセイントが全日制の高校へ進学するかという「計画進学率」を定めています。
それに基づいて高校の定員を決め予算化するのです。
ほぼ100%の生徒が全日制高校への進学を希望するようになりましたので、「計画進学率」を100%にすれば、高校入試は必要なくなり希望者全入が実現するのですが、100%には決してしません。
各都道府県が「計画進学率」を何%にしているか把握していませんが、私が現役の頃神奈川県では県民要求が高まり、92%から95%までアップしました。
ですから、5%の生徒は全日制高校には進学できない制度なのです。
そこで、全日制高校に行かれない生徒の受け皿になったのが、定時制と通信制の高校です。
かつて、定時制高校といえば、貧困家庭の子どもが働きながら通えるための高校でしたが、その役割が変わってしまいました。
ところが、定時制高校も統廃合の対象となり、通信制が増えました。
子どもたちは、5%にならないための受験競争と、〝名門〟高校に行くための受験競争に巻き込まれているのです。
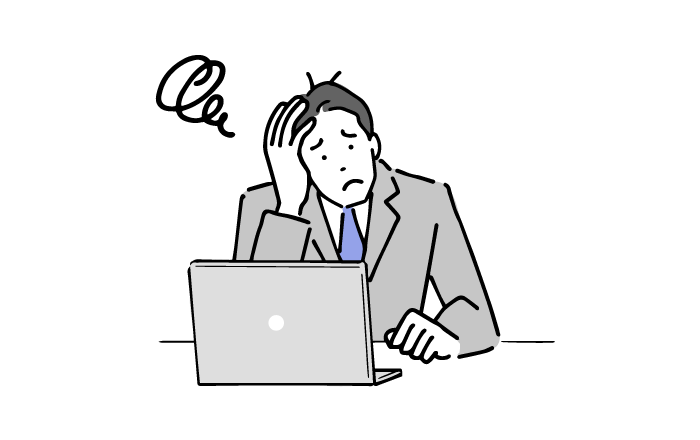
受験となったら、1点でも多く点数を取る競争になります。
教師は、親心で子どもたちを全力支援。
模擬テストを繰り返し、点数を取るためのテクニックを教えるために力を注ぎます。
点数をとるために、ひたすら〝おぼえる〟ことが大事だと教えることになります。
競争は、「成績」上位者にとっては、学習意欲につながるのかもしれませんが、多くの子どもたちにとっては競争に追い詰められ、ストレスを溜め込むばかりになるのではないでしょうか。
教師は、点数主義はよくないと思いながら、点数主義に陥っているのではないでしょうか。
理性と知性を身につけ感性を磨いて自立の力を育てるため、子ども同士が共に学ぶ、学び合うという共同体を築くという、教育の目的が歪められてしまっているのはないでしょうか。
親心で教師が〝受験競争を乗り越えるために!〟と点数を取るための〝勉強〟を強いてしまって、子どもたちは、学ぶ喜びや面白さ、学ぶことの本当の意味をつかむことができるでしょうか。
残念ながら多くの中学生が、高校へ進学したいが、勉強は嫌いだという矛盾のただなかに置かれているのではないでしょうか。
自戒の念を込めて言います。
教師がそれに加担しているとしたら、よかれと思ってしたことが、子どもたちを不幸にしている可能性があるのです。
教師もまた大きなジレンマに陥っているのではないでしょうか。
それをどう打開して、本当の教育を追究していくか。
まずは、それを自覚すること、知ることからでしょうか。



コメント