N中校長への書簡③
そろえることとそろえないこと
校長先生、またまたお便りします。
校長先生が常々仰っているように、学校の主人公は子どもたち一人ひとりであり、教職員一人ひとりの自主性が尊重されなければなりません。
例えば、昼食(給食)の時間。
N中ではどのクラスも、全員が授業と同じように全員が自分の席で前を向いて食べています。
どのクラスも、です。
それで、食事中喋るのはOKみたいで、喋りたい子は、喋りたい相手に向かって、席が離れていても喋るので、大きな声になるのです。
一言も喋らない子も多くいます。
担任の先生は、教室の前の方の自分の机で食べます、どのクラスも。
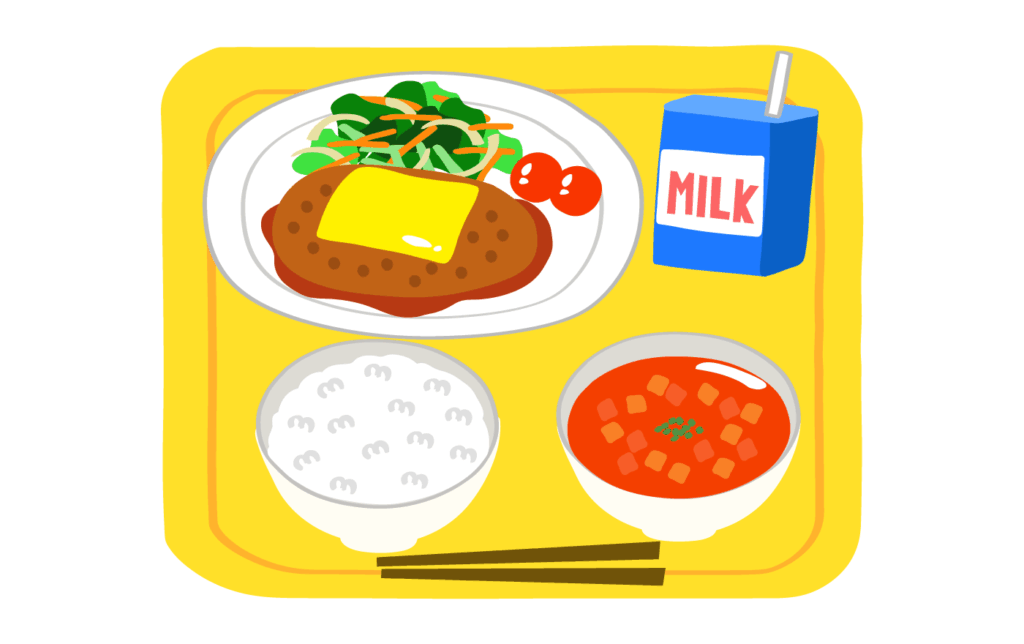
私が前に勤めていた学校では、私は会食にしたくて、班ごとに机をくっつけて、自由に喋りながら食事をとりました。
私は、きょうは1班、明日は2班、というように各班に行き、子どもたちの会話を聞いていることもありましたし、適当に会話に加わることもありました。
私はそうしたのですが、担任によって違いました。N中のように全員自分の机で移動することなく前を向いて食べているクラスもありましたし、自由に移動していいというクラスもありました。
ですから、1人で食べている子もいれば、2人で、3人でと、まったく自由なのです。
その頃は私がいたK県では中学校給食がなくて、子どもたちは弁当持ちでした。
ある子の弁当に梅干しが入っていて、「これがものすごく酸っぱいんです」と。
「へえー!」と私が言うと、「おばあちゃんが漬けた何十年物なんです。必ず入っているんです!」と。
イヤそうな、でも、そのおばあちゃんへの愛を感じる表情を見せてくれました。
またある子は、「きょうはコレか!」と。
「どうしたの?」と訊くと、毎日必ずぼくの嫌いなものが入っていて、食べてこないと怒られるんです」と。
お母さんの愛情が感じられました。
(くれぐれも言っておきますが、私は、弁当愛情論者ではありません。他県と同様中学校にも給食を!と要求してきました。)
弁当を忘れた子がいると、同じ班の子が音頭をとって、すこしずつおかずを提供してくれるよう声をかけ、その子が食べるものを集めてくれました。
N中では、昼食のとり方が、どのクラスも一緒なのです。
そろっているんです。
「1組では、そういう席で食べてるの?」「2組では…?」という話は、ついぞありません。
N中では、掃除の時間の5分前に放送が入ります。
「黙想を始めてください」と。
「黙想」とは「無言で考えにふけること」(広辞苑)。
何を考えるのでしょうか?
「きょうもまじめに掃除をやって、きれいにするぞ」
「邪念を払って、掃除に集中するぞ」
などと考えるのでしょうか。
うかつにも、子どもたちに訊いていませんでした。
「黙想」の時間に何を考えているのか、聞いてみたいと思います。
全校生徒が「黙想」して、そろっているのです(考える中身はそれぞれでしょうが)。
何のために「黙想」するのか、私には理解できません。
もし前にいた学校で「黙想」が導入されたら、私はやらなかったと思います。
担任の考え方で「黙想」をやらなくてもいいのではないでしょうか。
そのクラスの子どもたちの話し合いで、「うちのクラスは、やらないことにしました」というクラスがあってもいいのではないでしょうか。
そして、N中では掃除場所の分担が非常に細かく決められていて、2~3人の場所もありますが、ほとんど1人1カ所の分担制で、全校で個人個人の分担が決められています。
私がいた学校では、クラスごとに掃除場所が割り当てられ、あとは、そのクラスでどうやるか決めることになっていました。
掃除の時間を設けることには同意しますが、そのやり方をどうするかは、各クラスに任されていました。
私は、掃除も学級づくりの重要な活動ととらえていましたので、クラスで話し合うテーマの一つでした。
掃除の時間を設け教育の場の一つにするという考えはそろえるべきことでしょうが、掃除をどうやるかはいろんなやり方があってもいい、そろえるべきことではないと思います。
いろいろなやりかたがあって、それを学び合うことが大切ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
何が真実か、本当に正しいことは何なのかを深く考え判断する力を育てたい。
だから、子どもたち一人ひとり、教職員一人ひとりの考えを尊重し、それを出し合うことが大切であるという民主主義の論理で心をそろえる。
いろんな考えややり方があっていいのだということでそろえる。
そして、考え方はいろいろあり、やり方もいろいろあるので、そろえることはできない。
それを出し合い学び合うことが大切である。
そろえるべきことと、そろえるべきではないこととが、逆転している気がしてならないのですが…

自主性を認めよう、だから違いがあることを認めよう、という方針はそろえるべきことでしょう。
給食の時間をどうするか、掃除の時間をどうするかは違いがあっていい。
そろえることではない、と私は思うのですが…
兼好法師も、一律にそろえるのはよくない、なにごとも整っているのはよくない、と言っています。
弘融僧都は「物を必ず一律にそろえようとするのは拙いわざである。
物は不揃いなのがいい」と言った。これもまた卓見。
「なにごともことの整っているのはよろしくない。し残したところがある点にこそ趣があり、気持ちが安らぐ、内裏を造営するときも必ず造り終えないところを残すものである」と言った人がいる。
先輩たちのしたためた文書のうちにも章や段の欠けたものがある。
(兼好法師『徒然草 第82段』内田樹訳)



コメント