N中校長への書簡①
校長先生。
いつもお世話になっております。
先生は、私が出会ってきた校長の中でも、子どもも職員も一人ひとりを大事にする姿勢、多様性を尊重し受け入れようとする謙虚さ等、随一と言ってもよい先生です。
先生と共に仕事ができて、幸せだと思っております。
先生は、N中にあと何年いらっしゃるのでしょうか。
私は、50代になって、1年生から3年生まで受け持って、他の教員と共同・協働の関係を築き、3年間である程度まで変えることができるなと考えるようになりました。
「変える」というのは、もちろん、子どもが主人公になって自主的・自治的なクラス・学年・学校にしていくということです。
私は、校長などになる気はなく、学級担任をしたくて、さいごの年まで学級担任をしましたが、学校教育法で「校長は校務を司る」と定めてあって、絶大な権限を持っているのです。
もちろん、〝独裁〟になってはいけませんが、子どもと職員を大事にし、子どもたち一人ひとりに自立する力を育てるために、合意を得ながら、N中の良さを生かしながら、大胆に変えていくことができるのではないかと思うのです。
というのは、いま日本の教育が、戦後最大の危機を迎えている状況になっていると思えてならないからです。
N中も例外ではないでしょう。
一九九〇年代から、子どもたちは反抗の感情や行動を表に出さなくなり、群れることも少なく各人が内に籠ったかのようです。
問題が無いのではなくて子ども同士のちょっとしたトラブルに過敏に反応しつつ、それでいて教師にはいつも世話をしてほしいと密かに欲しているようで、子どものようすが複雑になってきました。こうした状況はことばで表現しにくいのですが、子どもの世界が息苦しい雰囲気に包まれているとでも言えばよいのでしょうか。
一九八〇年代のあからさまに荒れる子どもとはちがった意味で、関係の持ち方が難しいなと感じます。
この難しさは、二〇〇〇年代に入ってからいっそう強く感じるようになりました。
(女性教師へのインタビュー 今津幸次郎『教師が育つ条件』(岩波新書)13~14㌻)
私は、この部分を読んで、「N中だけじゃないんだ」「全国的な状況なのか?」と思いました。
2024年、小中高校生の自殺数は527人で、過去最高。
その原因の第1位は「学校問題」。G7では「10~19歳」で死因の第1位が「自殺」となっているのは日本のみです。
自殺を踏み止まった子ども、自殺を考えた子どもは、その数倍~数十倍はいたであろうと想像できます。
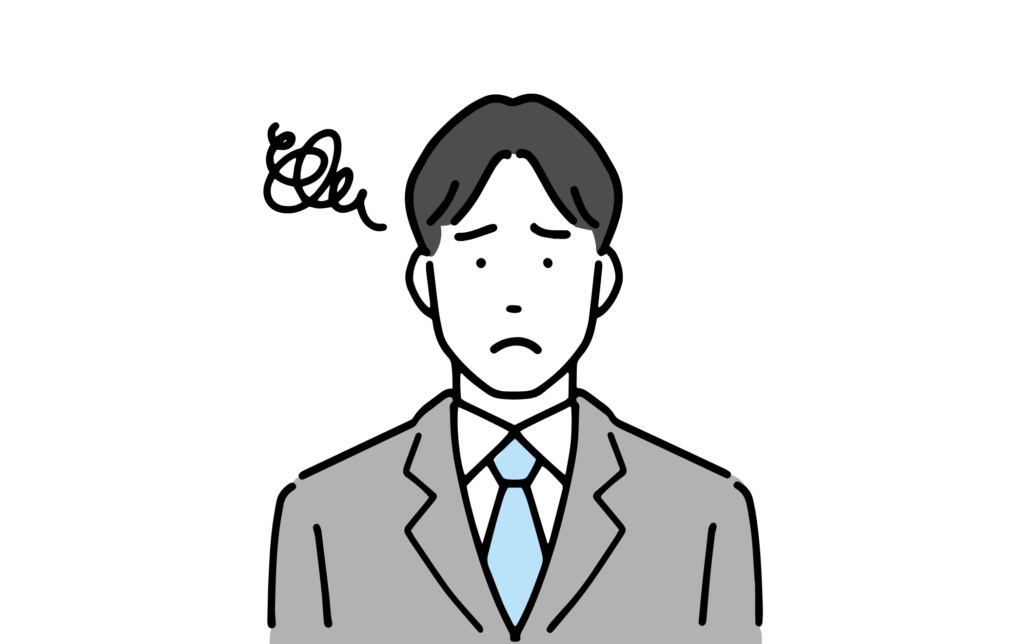
ユニセフの調査で、日本の子どもの幸福度は、調査した36カ国中、14位。
身体的健康では第1位なのですが、精神的な満足では32位となっています。
日本の子どもは、それほどまでに精神的に追い込まれているのです。
N中の子どもたちは、おとなしくて素直でとってもいい子たちですが、実は、かなりの部分、いやほとんど完全かもしれません、抑圧されているんじゃないかと、私は睨んでいます。
完全に抑圧されているから、子どもたちはそのこと気がついていないし、職員も気がついていない。
レールが敷いてあって、そこをどう進んでいくか、その部分だけ自分たちで考える余地があり、自主的にやっているように見える。
ですから、子どもたちが、新しい発想を生み出して、その厚い殻を破って、無限の可能性を育てていくということがないんじゃないかと思うのです。
これは、リーダーを育てていく時に、よく陥りがちなことです。
見ていると、子どもたちは、先生の指示に「ハイ、ハイ」と言って、よく仕事をこなしている。
そして、褒められる。真のリーダーは、自分で「こんなクラスにしたい!」「こんな学校にしたい!」という夢をもって、各自が自分の夢を出し合って、語り合って、「それじゃあ、こんどの文化祭はこうしよう!」と自分たちで決めていく。
そうして、少しずつでも学校が変わっていく。
昨年、3年生で「公民」の最初の時間に、「何にたいしてでもいい、自分の願いを出してください」と言ったら、「(学校にたいして)無言清掃はやめてほしい」と誰かが言いました。これに賛否を問いましたら、ほとんどの子が「賛成!」と言いました。子どもたちは、いろんな思いをもっているのです。
それを出せない、既定路線ができあがってしまっているから。
例年どおり、例年どおり。
これもまた、学校が変わらない大きな壁でしょう。
わたしも、前任校で「例年どおり」には本当にまいりました。
でも「子どもたちに話し合わせましょう」には反対はありませんでした。そして、子どもたちが生き生きと変わっていく、感動を生み出していく場面に遭遇して、職員も変わっていきました。
NHKで放送中のドラマ「舟を編む」を見ました。
ある出版社で辞書をつくっていく話です。
主人公は「恋愛」という言葉の説明に疑問を感じました。
ほとんどの辞書は、「恋愛」を「男女」や「異性」の間の関係と説明していました。
これでは、同性愛の人が除外されていると。
編集部で議論し、再検討することになりました。
ドラマの大事なキーワードは「疑う」。
上司は「疑え!」「全て疑え! とことん疑え!」と強調します。
なぜか?「信じられる辞書をつくるために!」。
「疑う」ことが「信じる」ことにつながる。
教育も同じではないかと思います。
いまやっていることは本当に正しいか? 真実は何か? すべてを疑うことから、始めてはどうでしょうか。
すべてを疑うことから!

私も、毎回授業をやって、「この授業は正しかったか?」と疑うことにしています。
「まちがっていた!」ということもあります。
N中には、よい面があります。
子どもたちの質は非常に高い。
ものごとを受け入れる素地があり、行動力もあります。
伸びる可能性を秘めています。リーダー候補が多くいます。
私の当面の夢は、子どもたちが眼を輝かせ、大きな深い感動を生み出し涙する、先生たちもその感動に酔いしれる。そんな光景を夢みます。
心が震えるほどの感動を!
それは、学校でしかできません。
その感動は、子どもたちをいつまでも励まし続けるでしょう。
乱筆乱文、お許しください。
久永 理



コメント