勉強について考える(11)
中学校で九つの教科がおかれているわけ(つづき)
もう少し、〝つづき〟がありました。
だれにでも、多少の教科のすききらい、得意不得意はあるだろう。
しかし、こういう意味で設けられている教科の役割は、それぞれかけがいのないものだから、すくなくとも義務教育の段階で、「ぜったい好きになれない教科」や、「投げてしまう教科」は、つくるべきではない。
というのは、それは、たいていの場合、先生の責任も大きいと思うが、おもしろさを知らないだけだから、たとえば女子の一部が、数学がきらいだとか、理科はやる気がしないとか、男子の一部が、国語の時間に小さくなっている——-とかいうのを、そのままにしておいてはいけないと思う。
ほとんどまともに授業を受けようとしなかったり、さわぎたてたりするのは論外だし、一部のひとにそういう態度があれば、みんなの勉強がひどく妨害されるのだから、おたがいにそれを許してはいけない。
近ごろ、「能力・適性に応じて」ということをしきりにいう人たちがいるのだが、いろんな可能性があるのに、はやく見限って、この子はこの程度でいいとか、そこまでやらせるのはむりだとか、勝手に決められたら、迷惑だろう。
きみたちの中にも、ちょっとわからないとすぐ投げ出して、「自分に向いてない」なんていう人がいるが、はやまらないほうがいい。
「適性」ってものがあるとしても、そんなものはひとりでにあらわれてくるものではない。
いろいろなことをがんばってやり抜きなかで、見えてくるし、つくられてくるものだ。
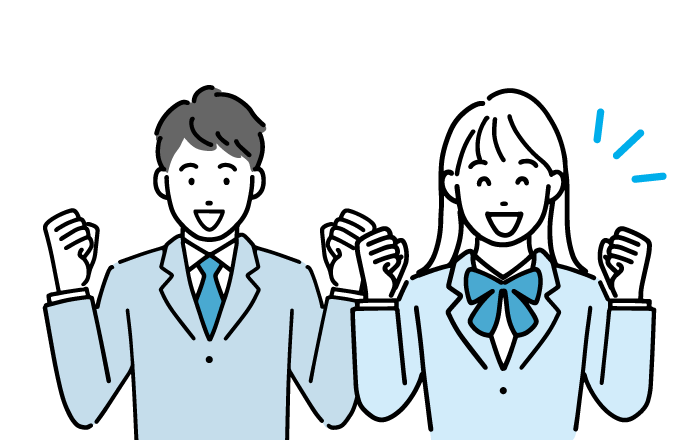
どの教科だって、楽しく、充実感をもって学ぶことは、きっと可能なのだ。
先生たちも、きみたちにそれを実感させることができるようにがんばる。
きみたちもがんばってほしい。(おわり)
やる気の出る4条件
健康な体と心
かぜをひいていたり、虫歯があったり……体の中に病気をもっていたら、やる気が出ません。
心配事をかかえこんでいても、集中できません。
体と心の健康が第一です。

めあて(目標)をもつ
めあてのない勉強は、やる気が出ません。
自分に対して責任んがないいから、いつでも中断できます。
「今度の期末テストで80点以上とるぞ」といったものから、将来の目標にいたるまで、いつも目標・課題をもつことです。
基本的な生活習慣づくり
生活リズムがくずれているとやる気が出ません。
夜更かしの朝寝坊、食事の時間も一定していなし、遅刻や忘れ物が多い。
あまりに不安定な生活。
これでは勉強は無理です。
学習の土台は、この基本的な生活習慣づくりにあります。
基礎学力の回復
基礎学力が不足しているために、やる気が出ない場合があります。
さあがんばろうと机に向かっても、たちまち障害にぶつかって進まない場合があります。
漢字の読み書きや四則計算でつまずいている例は多いのです。
基礎学力の回復は、やる気・自信に直結するものです。



コメント