道徳教育について考える(4)
道徳の教科化について〔3〕
「道徳」教科化への政策動向とその批判㊦
立憲主義の危機のもとですすむ教育改革
櫻井 歓(日本大学)
公教育の全面的統制の一環として
こうしたなか、行政権力による、公教育の全面的統制といえるような教育改革がすすめられつつあります。
それは、地方教育行政に対する自治体の首長の権限を強化する教育委員会制度の変更や、教科書に政府見解や最高裁判例にもとづいた記述をさせるという社会科系教科の教科書検定基準の改定、といった形で端的に現れています。
「道徳」の教科化も、現在強化されつつある、行政権力による公教育統制の一環として捉えることができます。
「道徳」が教科化された場合、授業内容への規制強化、検定教科書の使用の強制、そして子どもの人格評価にも及ぶ成績評価といったことが懸念されます。
これらの教育改革を通じてねらうところは、愛国心の育成を中心とする〈戦争ができる国づくり〉ではないでしょうか。(これを杞憂と思わせないような事例として、2013年7月に自衛隊での宿泊防災訓練をおこなった東京都立田無工業高校の事例があります)
(また、防衛省が全国の自治体にたいして、18歳になった住民の名簿を出させる動きがあり、多くの自治体が本人の承諾無しで提出していることが明らかになりました。
さらに、防衛省は全国の中学・高校を訪問し、自衛隊への勧誘活動を行っています。
自衛隊に入るかどうかは、あくまでも各個人の判断に委ねられることですが、子どもを、戦争することが本来業務である自衛隊に送るようなことが許されるでしょうか。
なによりも命を大事にし、いかなる暴力にも反対する本来の道徳の精神に悖ることですし、徹底した平和主義の憲法を遵守する義務を負う公務員としても絶対にできないことです。――久永)
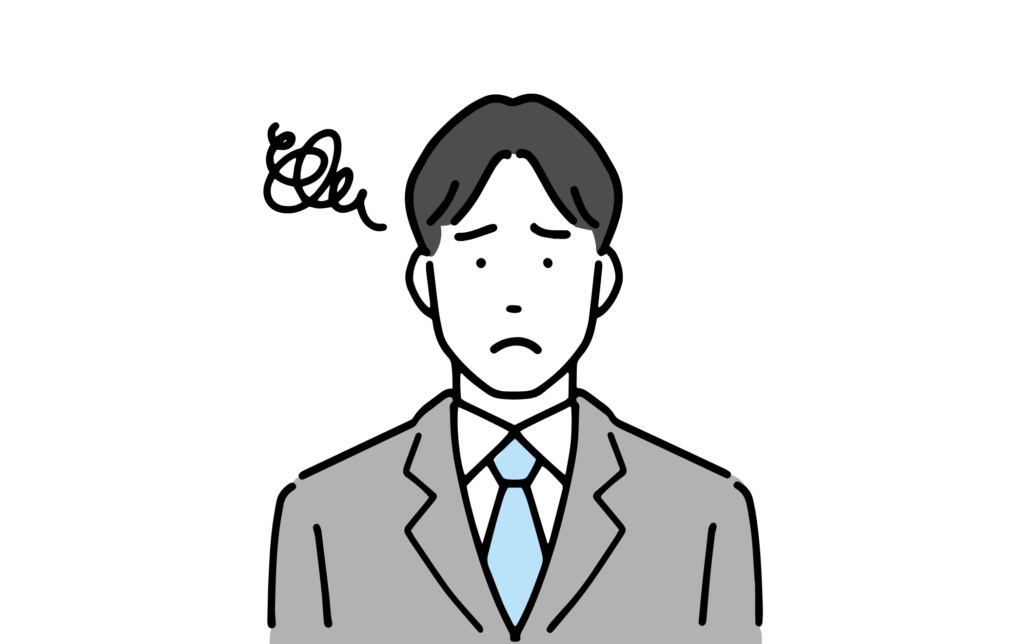
公教育をどこまでもコントロールすることを当然とするかのような昨今の教育改革に欠けているのは、民意を代表するとされる多数派の意思や、それを執行するとされる行政権力によって侵されてはならない精神的自由(良心の自由、表現の自由など)があるという感覚です。
そのような人権を守ろうとするのが立憲主義の考え方ですが、安倍政権はこれを否定する方向ですすみつつあります。
(注:この論文は2014年に書かれました。実際、安倍政権はこの指摘のとおりに「教育改革」をすすめ、その後の菅内閣、岸田内閣もこれを継承しています。当初から反対世論が大きかった「教員免許更新制」は2022年7月に廃止されました。)
このように捉えるとき、「道徳」教科化の問題は
- 立憲主義を否定する「憲法改正」への志向(国家のフレーム自体の改変)
- 教育委員会制度などの改変を含む公教育の全面的統制
- その一環をなすイデオロギー統制としての「道徳」教科化
というように、多層的に把握することができます。
いま起きているのは行政権力の暴走といえるような事態であり、「道徳」の教科化もその一環としてあるのです。
当事者の自主性を尊重する社会的合意を
文科省が発行した「私たちの道徳」は、こうした状況のもとでつくられた、事実上の国定教科書です。(2018年から小学校で、2019年から「道徳」の教科化が実施され、文科省検定済教科書が発行されました ――久永)
この教科書では、道徳教育をすすめる有識者の会編「13歳からの道徳教科書」「はじめての道徳教科書」(育鵬社、2012年、2013年)との間で、多数の題材が共有されています。それらの特徴は、ポジティヴなモデルと見なされる日本人に焦点を当てて顕彰する点です。

一方、育鵬社の「パイロット版教科書」では複数採録されている天皇・皇族に関する題材や、国家のための自己犠牲を称揚するような題材が、「私たちの道徳」では基本的に採録されておらず、文科省として一定の抑制をしていると見える面もあります。
「私たちの道徳」は、今後「道徳」が教科化された場合に当面のモデル教科書となるものですが、将来的に民間の検定教科書が出版される場合には、より復古的・反動的な内容の教科書が出てくる可能性は十分にあります。
しかも、地域によっては、自治体の首長の意向を反映させる形でそのような教科書が採択されていく可能性があります、道徳教科書の問題は、教科書検定・採択制度、教育委員会制度とも結びついた問題であるといえます。
現在、教育行政に対する首長権限が強化される状況であればこそ、公教育の当事者である子ども、教師、保護者の自主性を尊重する社会的合意をつくっていくことが、暴走する行政権力から公教育を取り戻すうえで、ひときわ重要な課題となっているものと考えます。 (おわり)



コメント